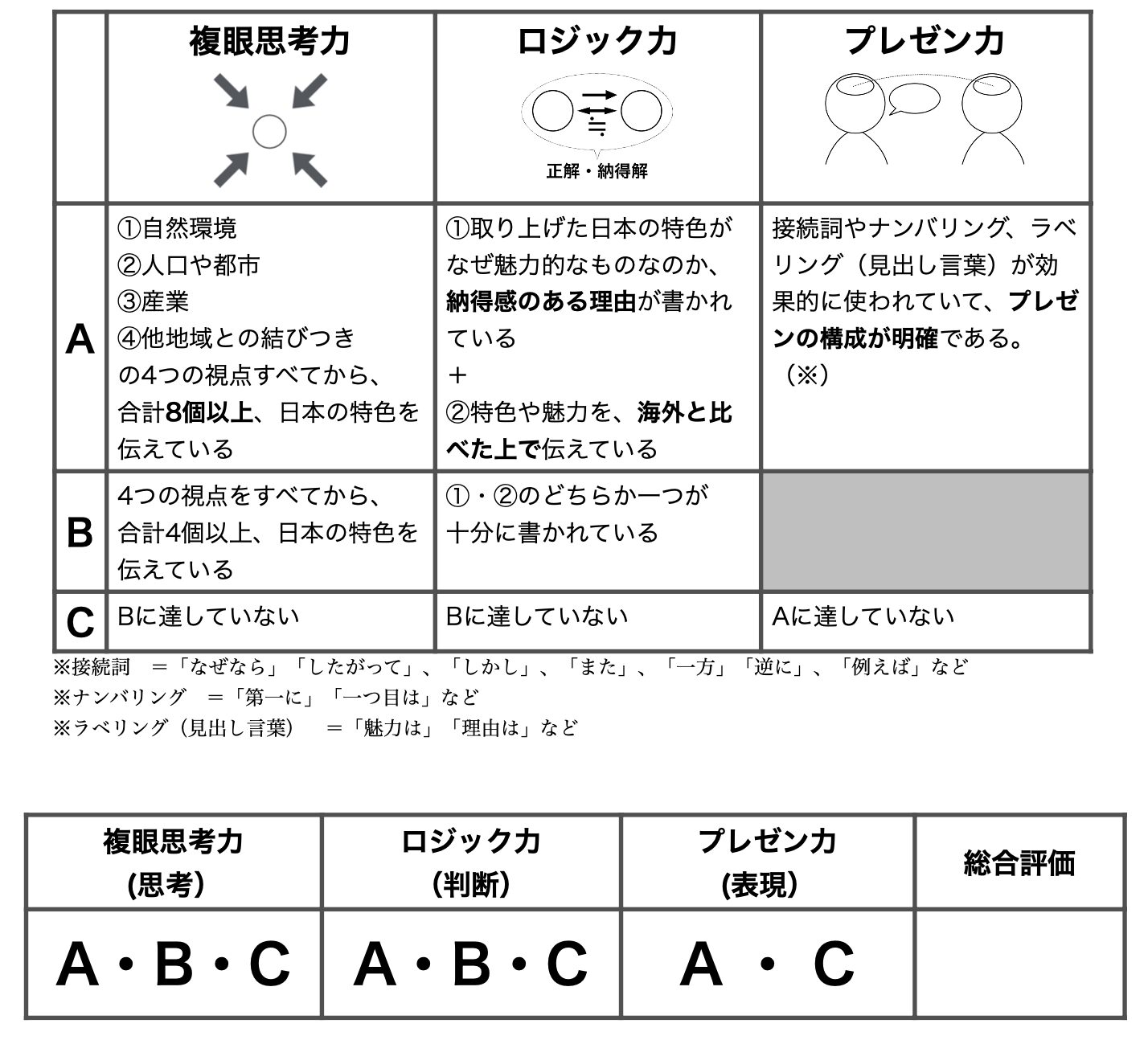社会科教員の役割とは?「わかりやすく教える」以外に何があるのか?
社会科は「社会の問題を発見し、解決して、幸せを増やす」ためにある。
そのためには、「地理」「歴史」「公民」を学び、「自分はこう思う」と言えるようになることが必要。
では、そうした学びを支える社会科教員の役割とは何だろうか?
僕は、大きく分けて3つあると考えている。
①目の前の生徒にわかりやすく教える

今や、優れた教材が世の中にあふれている。さらに、生成AIの登場によって、どんなに難しい内容でも分かりやすく説明してもらえる時代になった。
正確な情報を伝えるだけであれば、良質な動画教材を一本見させれば十分。生徒はそれを見れば、知識の習得をある程度できるはず。
でも実際の教室では、それだけではうまくいかない。
なぜなら、生徒一人ひとりは異なる興味・関心や前提知識、認知のクセ(素朴概念や誤解)を持っているから。
気分や体調によっても理解度は左右される。例えば、1時間目に社会科の授業がある時と、体育の後の6時間目に社会科の授業がある時とでは、生徒の状態は異なるだろう。
同じ教材を与えても(同じ授業をしても)、全員がいつも同じように理解できるわけではない。
だからこそ、教員の存在が必要になる。
生徒の状態や特徴をふまえながら、「どうすればこの内容が伝わるか?」を考え、学びを設計する。生成AIや良質な授業動画が提供する「オーソドックスな、わかりやすい教え方」を、目の前の生徒に合わせてカスタマイズする。
これこそが現場の教員に求められる役割であり、ここに現場の教員の価値がある。
「普通の教え方」から逸脱することを怖がらなくていい。1から10まで丁寧に教えなくてもいい。「教科書に書かれていることは全部扱っておかないといけない」なんて思わなくていい。
tribial(些細)なこととcrucial(重大)なことを区別し、目の前の生徒の心に刺すことだけをとにかく目指す。これは現場の教員だからこそできることだ。
とは言っても、わざわざ教員があれこれ考えてカスタマイズせずとも理解できる生徒が、教室にはたくさんいる・・・というのも事実である。「わざわざ教員が教えなくても、オンライン授業を使えばいい。学校は不要」と断言する堀江貴文氏(ホリエモン)の主張は決して的外れではなく、むしろ的を見事に射ている。
「いや、生徒に勉強させることが大事なんだよ。オンライン授業とか動画授業とかがあっても、生徒は自らそれを使おうとはしないんだよ。だから生身の教員が実際に授業しなきゃいけないんだ」って思う人もいるかもしれない。しかし、だとしても、一人一人にタブレットで授業動画を見させて、現場の教員は教室を巡回して「勉強させる」役割に徹すれば十分だ。
AIや動画教材によって、「教員がわかりやすく教える」ことの価値は確実に下がっている。
そこで、僕が今後、より重視すべきだと思っているのは以下の点だ。
②生徒が「ポジションを取れる」ようにする

社会科の目標は「自分はこう思う」と言えるようになること。
社会の中で何が「問題」かは人によって感じ方が違うし、その解決方法にも唯一の正解はない。
「これ問題だと思う。問題を解決するために、このやり方がベストかどうかはわからないけれど、今の時点では自分はこうするべきだと思う」
こんなふうに、たとえ迷いながらでも、自分の立場を表明すること。そこから社会は動き出す。
その練習を積み、その力を育てるのが学校の役割であり、教員の役割だ。
まずは、生徒がポジションを取れるテーマを設定すること。
そして、自分の考えを持つために必要な知識や視点を、順序立てて学べるプロセスを設計すること。
教科書に書かれている知識だけをなぞるのではなく、見解が分かれ、摩擦が生まれるかもしれない問いをあえて扱う。

なお、生徒が自分の意見・解釈を言い合う場をつくることで、教室が「小さな社会」となる。
お互いに意見・解釈を出し合い、時に対立することで、人それぞれ価値観が異なることや、自分が良いと思った解決策では困る人がいる、という「社会」のリアルを体験的に学ぶことができる。
そして、いろんな人がいる「社会」の中でいかに合意や妥協を導くか、というプロセスを経験することができる。
こうした学びは、集団で学ぶ「学校」だからこそ実現できる。
一人で知識を身につけるなら、個別最適化されたAI教材の方が効率的かもしれない。でも、社会の中で意見を持ち、他者と向き合う練習は、教室というリアルな空間でしかできない。
もちろん、オンラインでも意見交換はできる。けれど、表情や声のトーン、間などの「空気」は対面だからこそ伝わる。そこにこそ深い学びがある。
時には、生徒同士のやりとりが議論から言い合いになることもあるかもしれない。そうしたときにファシリテーションや調整を行うのも、社会科教員の(というか大人の)役割だ。
ただし、ポジションを取れるようにテーマを選定し、学習プロセスを設計し、議論を見守るだけでは不十分。
そもそもそのテーマに関心がなければ、生徒は本気で考えてくれない。
そこで必要になるのが、次の役割である。
③好奇心を引き出し、学びへと導く

どれだけ良い教材や優れた授業計画があっても、生徒に「学びたい」という気持ちがなければ意味をなさない。
学習意欲がある生徒でも、すべての単元に自然と興味が湧くわけではない。「このテーマ、何のためにやるの?」と感じることもあるだろう。
だからこそ、授業の導入が重要になる。
最初の数分間で、「お、ちょっと面白そうだな」と思わせられるかどうかが、その後の学びを左右する。
まとめ
社会科教員に今もっとも求められているのは、次の3つの力。
- 生徒の好奇心を引き出すような授業の導入を工夫すること
- 生徒が「自分はこう思う」と言えるように支援すること
- 教室の中で生まれる対立や意見交換を丁寧に調整・支援すること
「わかりやすく教えること」は、もちろん今でも大事。
でも、それ以上に、生徒が社会と自分との接点を見出し、自分の言葉で考えられるようにする――そうした力を育てることこそが、社会科教員の本質的な役割だと思う。
参考文献
今井むつみ(2016). 『学びとは何か――〈探究人〉になるために』. 岩波新書.