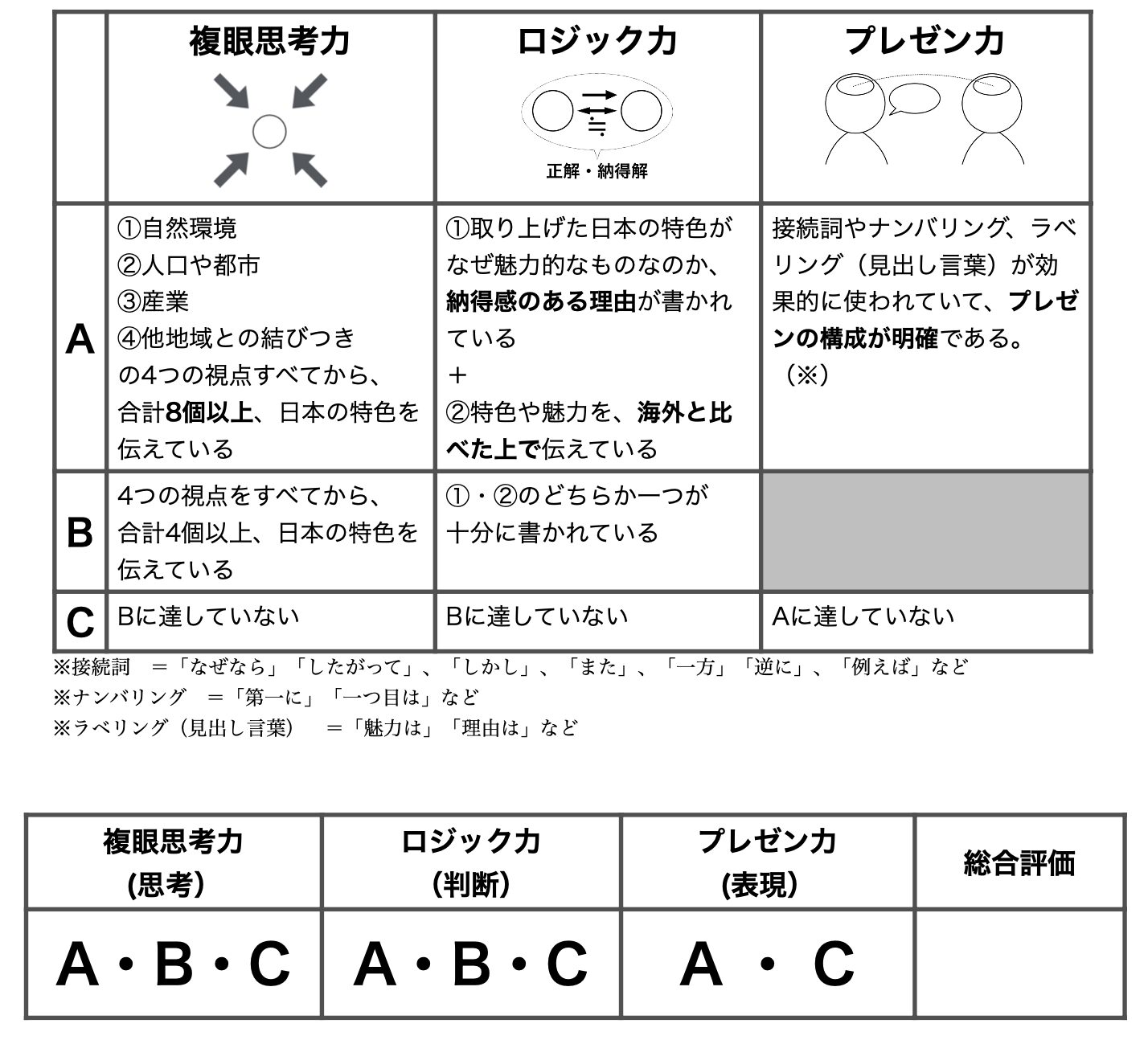生徒に「歴史を学ぶ意味って何なの?」と聞かれたら

「先生、なんで歴史を勉強するんですか?」
社会科教員なら一度は聞かれるやつ。
この問いはただの雑談や文句じゃなくて、自分が学んでいることに意味があるのか、これが将来にどうつながるのかを確かめたいという、まっすぐな気持ちから出てきたものだと思う。
ある意味、「試されている」質問。
この先生は納得感のある回答をしてくれる大人かどうか、を。
そんな時に、その場しのぎの形式的な回答をしたら「この人は真剣に受け止めてくれない人なんだな」と思われてしまう。

また、
「受験に必要だから」
とか、
「大人になったら、意味がないと思えること、理不尽なことにも耐えなきゃいけない。だから大人になる前に”耐える練習”をしているんだよ」
みたいに、明らかに本質からズレているだろ…っていう回答をするのも避けたい。
また、自分が歴史好きだからといって、
「歴史ってすごく面白いんだよ!昔ね、〇〇って人がいてね…」
と一方的に話してしまうのも、(絶対ダメだとは思わないけど)生徒には響きづらいと思う。
生徒が求めているのは、「この教科が、自分にとってどんな意味を持つのか」ということ。
では教員としてどうするか。
真剣に向き合う
生徒の中には「なんとなく雑談の流れで」聞いているだけの人もいると思う。
でも、「なぜ歴史を学ぶのか?」というのは社会科教員にとってすごく大事なテーマ。
だからこそ真剣に向き合う。自分の仕事の「ど真ん中」にある問いをいい加減には扱わない。そういう姿勢を見せたい。
ということで、「核心に迫る問いをぶつけてくれてありがとう!」って感謝の気持ちを伝えた上で、
生徒に聞いてみる
いきなり自分の答えを語りはじめるんじゃなくて、まずは生徒の考えを聞いてみる。
「僕なりの考えはあるけど、まずはきみはどう思う?なんで歴史を学ぶんだと思う?」
このように聞き返し、生徒を子供扱いせず「一人の人間」として尊重する。
その上で、返ってきた答えに共感できる部分があれば、「あー、それわかる!」と素直に共感する。
「へえ、そんな考え方もあるんだな」と感じたら、「なるほど…!勉強になった」と伝える。
そのあとに、自分の考えを伝える
生徒の考えを受け止めた上で、自分の考えを伝える。
そのときは、大きく2つの視点で話すのがいいと思う。
- 社会全体の中で、歴史を学ぶ意味(本質的な話)
- 自分の生活や楽しみとつながる意味(個人的な話)
ただ、ちゃんと話すと長くなるので、あらかじめ「短くまとめるか、ちょっと長めにじっくり話すか、どっちがいい?」って聞いてみてもいい。
話をしている最中も、生徒の反応を見ながら調整する。
以下、質問への回答の僕なりの切り口。
歴史を学ぶ理由についての僕の考え
本質的な話
①問題を解決して、より良い未来をつくるため

本質的に言えば、より良い未来をつくるために歴史を学ぶのだと思う。
たとえば、友達が何かに困っていたとして、その人を助けたいと思ったとき、
- 今までその人がどんなことをしてきたのか、
- どういうやり方でやってきたのか
そういう「過去」を知らないと、適切なアドバイスはできない。
少し話は逸れるが、自分のことを全く知らない「著名人」に人生相談をしても意味はない。その人の過去=歴史を知らないことには、百戦錬磨の「著名人」でもアドバイスしようがないから。
これは社会全体にも当てはまる。
社会にある問題を解決するには、現在の状況だけでなく、その背景や成り立ちを知らなければならない。
社会科は「問題を発見し、解決して、幸せを増やす」ための科目。
- その地域の自然環境や地理的な条件(地理)
- 昔から積み重ねてきた経験や価値観(歴史)
- 今の社会のルールやしくみ(公民)
こうした背景を知らずに、問題を発見・理解することも、解決することもできない。

だからこそ、社会科では「地理」「歴史」「公民」という3つの分野を学ぶ。
僕たちは地理・歴史・公民の分野の学習を通して、
- 幅広い知識を身につけ、
- 知識を関連づけて分析・思考する能力を伸ばし、
- 社会や歴史に対する想像力を養う。
そうすることで、「社会の中で起きている出来事(=社会現象)」を捉える目が養われ、「どうすればよい方向に向かえるか?」を構想できるようになる。
② 人間という生き物への理解が深まるから

もうひとつの理由は、歴史を学ぶことで人間という存在を深く知ることができるから。
もし人間が単純なルールで動く存在であれば、理解はとても簡単。たとえば「1万円札を見せれば誰でも言うことを聞く」みたいな単純な生き物だったら、人間社会はもっとわかりやすいはず。
でも、現実はそうではない。
僕たちは、親しい友達や家族のことですら実は完全にはわかっていない。むしろ自分自身のことすら、よくわからないことがある。
人間の行動には予測できないことがたくさんあるし、誰にでも当てはまる絶対的な法則なんてない。人間は複雑で不思議な生き物。

そんな人間がたくさん集まってできているのが「社会」。僕たちはその社会の中で生きている。
だからこそ、人間という存在について理解を深めようとすることには大きな意味がある。
歴史を学び、過去のさまざまな人たちの行動に想いを馳せることで、人間という生き物への理解が少しずつ深まっていくと僕は信じている。
個人的な話
ここまでちょっと大げさで壮大な話をしてしまったが、もっと身近で個人としてのメリットもある。
③ 過去の世界の中に入るのが面白い
たとえば、過去の世界を追体験できる面白さがある。
人間がつくってきた物語や事件を知るのは、単純に「読み物として」面白いと思う人も多いはず。
④ 歴史を知っていると旅行が楽しくなる
僕が一番のメリットだと思っているのがこれ。旅行が楽しくなる。

例えば沖縄旅行について考えてみる。
沖縄の美しい海を見て、それだけで「楽しい!」と感じるのはもちろんアリ。むしろそういう楽しみ方の方が普通だと思う。
でも、歴史を少し知っていると見えるものが増える。

- 沖縄にはモノレール(ゆいレール)はあるけど、地下鉄がない → 車社会だったアメリカに占領されていたから? 地下に埋まる不発弾のせい?
- 沖縄はリゾート地のイメージが強いけれど、太平洋戦争の沖縄戦があった場所でもある → 平和祈念資料館などを訪れてみたくなる
- 沖縄には豚肉料理が多い → 琉球王国時代に中国との交流があったから?

さらに、オリオンビールの看板を見て、こんなふうに考えることもできる。

- なぜ本土の有名ビール会社(キリンとか)があまり見られないんだろう?
- 戦後の占領や本土復帰の影響があるのかな?
- 沖縄の地元企業を守るための仕組みがあるのかも?
実際にこういう楽しみ方をするかどうかは別として、社会科の知識があると旅を楽しめる幅が広がるのは間違いない。
歴史の知識、社会科の知識・考え方を持っていると、世界の見え方そのものが豊かになる。
まとめ
いろんなことに気づいたり考えたりするのが楽しいかどうかは、人それぞれ。
でも、歴史を学んでおくと人生を楽しめる選択肢が増える――僕はそう思っている。
そして、より良い未来をつくるためにも、複雑な社会や人間について理解を深めるためにも、歴史を学ぶことには確かな意味があると信じている。