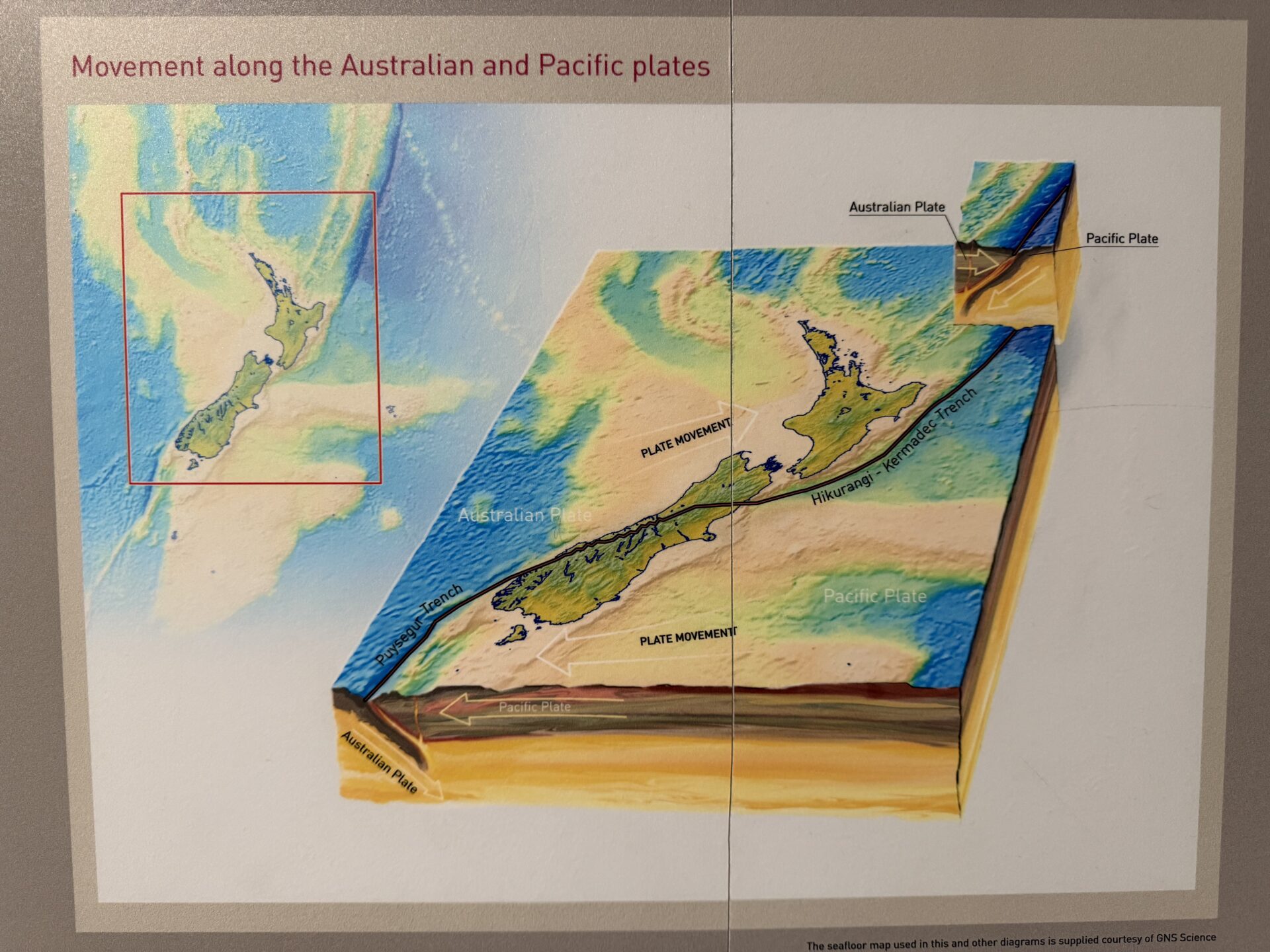東南アジアの経済と現状をわかりやすく

現在の東南アジアは、
- 熱帯ゆえの農産物の産地としての重要性や、
- 工業製品の製造拠点としての重要性、
- 市場としての重要性
をもつ地域として世界から注目されている。

東南アジアは貴重で価値が高い地域
農産物の供給地として重要
世界には熱帯地域でしか育たない作物が多く存在する。
たとえば
- アブラヤシ(パーム油)
- コーヒー
- コメ(熱帯の水稲)
そうした熱帯性作物の供給地として、東南アジアの存在は非常に重要である。
地球儀やマップアプリで地球を眺めると、赤道付近にまとまった陸地が存在するのは、主に東南アジア、ラテンアメリカ、そしてアフリカの3つの地域に限られることがわかる。つまり、地球上で熱帯気候に分類されるエリアは意外と限られている。

この中で、先進国の人々にとって最も「使いやすい」地域と言えば、東南アジアだろう。東南アジアは政治的に安定している国が多く、巨大市場である中国やインドに近いという地理的優位性もある。
- 一方、ラテンアメリカは治安の悪さや政情不安が課題で、さらに中国やインドからも遠い点がネック。
- アフリカは中国やインドに比較的近いため地理的なポテンシャルは高いが、治安や政情の不安定さがより深刻。
東南アジアは、地球上でもめずらしい熱帯気候の広がる地域であり、かつ「利用しやすい」のである。
→東南アジアの農業をわかりやすく:なぜプランテーションが盛んなのか?
工業製品の製造拠点として重要
さらに東南アジアは、農業だけでなく工業製品の生産地としても世界的に注目されている。その背景には、いくつかの要因がある。
- 人口が多く、労働力が豊富
- 賃金が比較的安く、生産コストを抑えられる
- 教育水準が高く、技術力のある労働者が多い
- 各国政府が外国企業の誘致に積極的(税制・インフラ整備など)
- 原材料も地域内で調達しやすい
このように、東南アジアは「安くて優秀なモノづくりができる場所」として、多くの多国籍企業に選ばれている。
※しかも、東南アジアの国々は経済発展のスピードや段階に差があるため、企業にとっては長期的に魅力のある製造拠点でもある。「東南アジアに投資する価値」は今後もしばらく続くと考えられている。

市場として重要になりつつある
かつては「安く作れる場所」としての価値が中心だったが、近年では「売れる場所」としての価値も高まっている。
東南アジアはもともと人口が多い上、近年の経済発展により中間層が急速に増えているからである。
※しかも、東南アジアの国々は経済発展のスピードや段階に差があるため、企業にとっては長期的に魅力のある市場でもある。「東南アジアに投資する価値」は今後もしばらく続くと考えられている。

現代の東南アジアの各国について
東南アジア諸国は、それぞれの国が異なる役割を持ち、システムのように連携して機能している。
※とりあえずシンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピンについて理解しておけば十分だと思う。
シンガポール

- 地域統括本部・お金を集める場所
- 物流と人の流れのハブ(航空・港湾)
早くから工業化に成功したが、労働集約型産業では周辺国に勝てなくなることを考え、知的産業や金融中心のポジションへとシフトした。
タイ

- 自動車産業の拠点(「アジアのデトロイト」)
- 稲作
マレーシア

- 半導体と電子部品(←労働集約的)
- アブラヤシ栽培とパーム油(←労働集約的)
- 原油
ベトナム

- 縫製(←労働集約的)
- 電子機器の組み立て(←労働集約的)
- コーヒー豆(←労働集約的)
- 稲作
インドネシア

- アブラヤシ栽培とパーム油(←労働集約的)
- ニッケルなどの鉱産資源
EV(電気自動車)に不可欠なニッケルが多く採れるため、今後ますます注目される。
フィリピン
- 英語力を生かしたBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の拠点
- 海外出稼ぎ労働者(OFW)の送り出し国
英語が公用語なので、コールセンターや事務処理業務の委託先として世界中の企業が注目。
多くの労働者が海外で働き、母国に送金して経済を支えている。