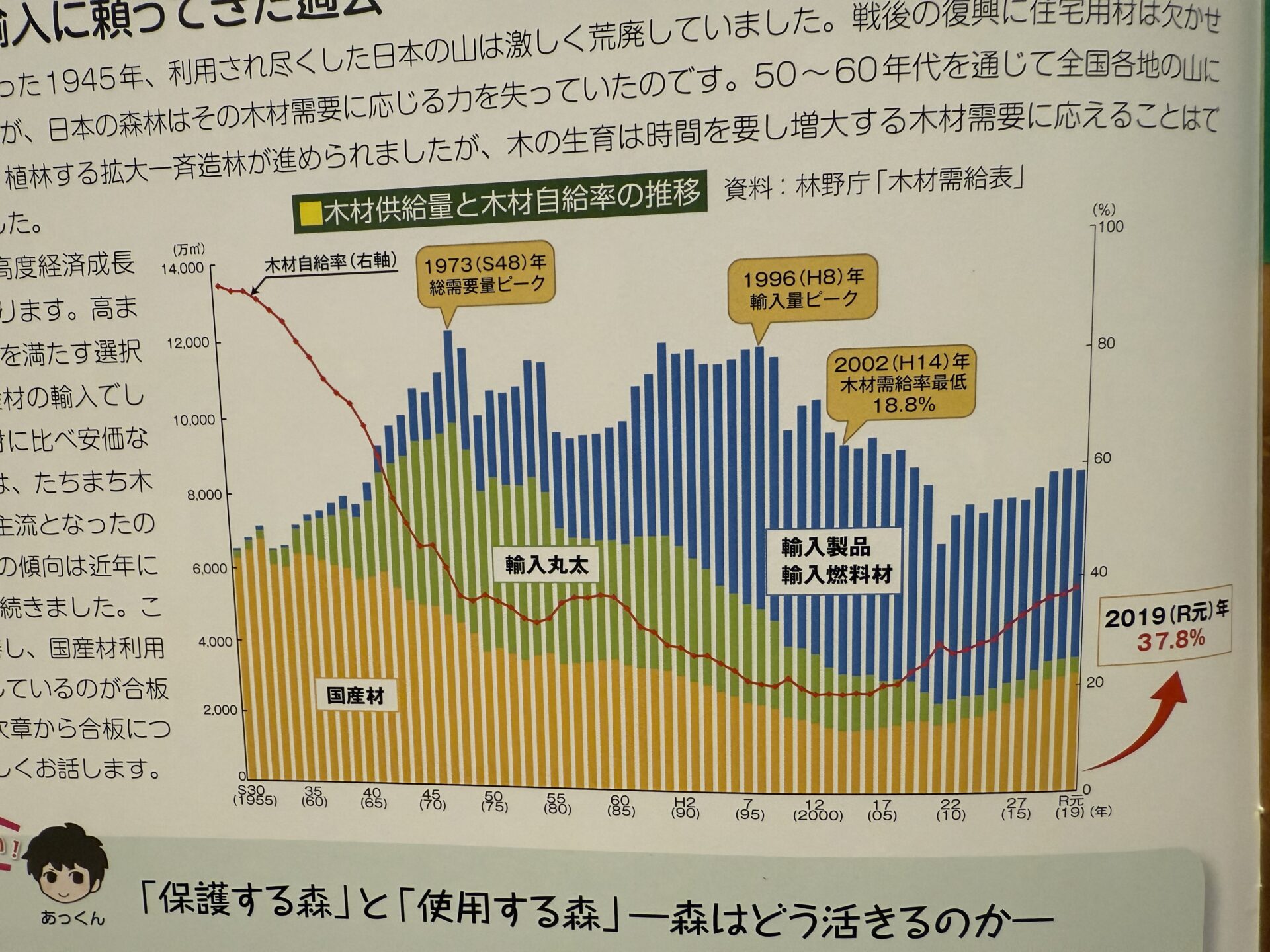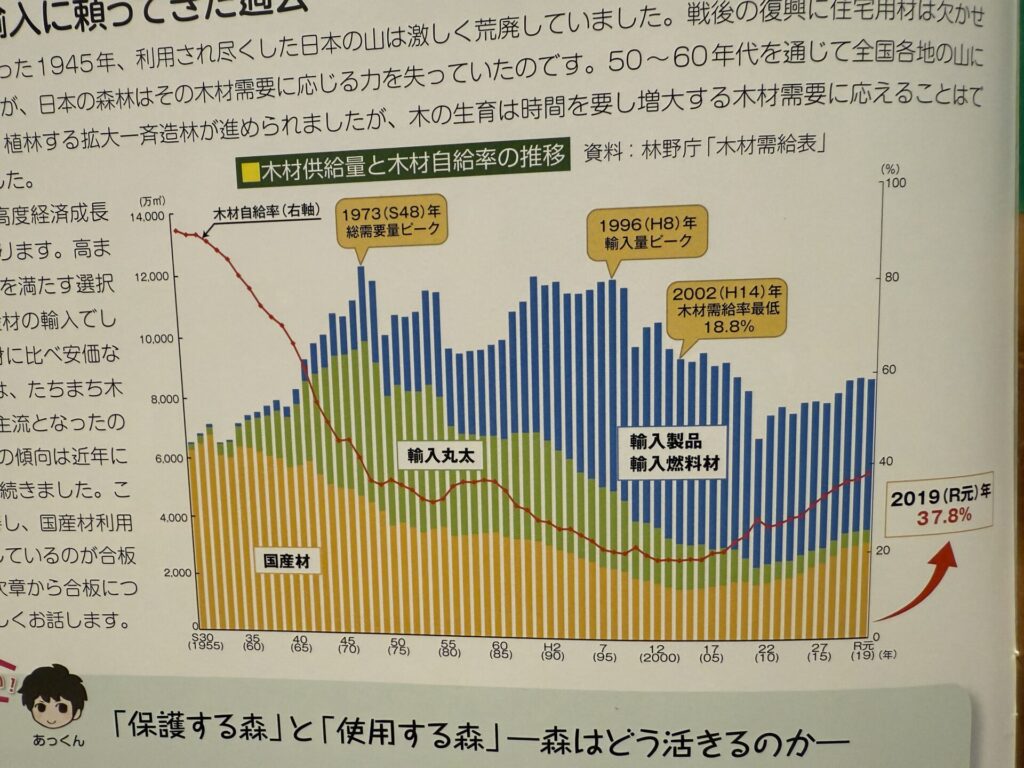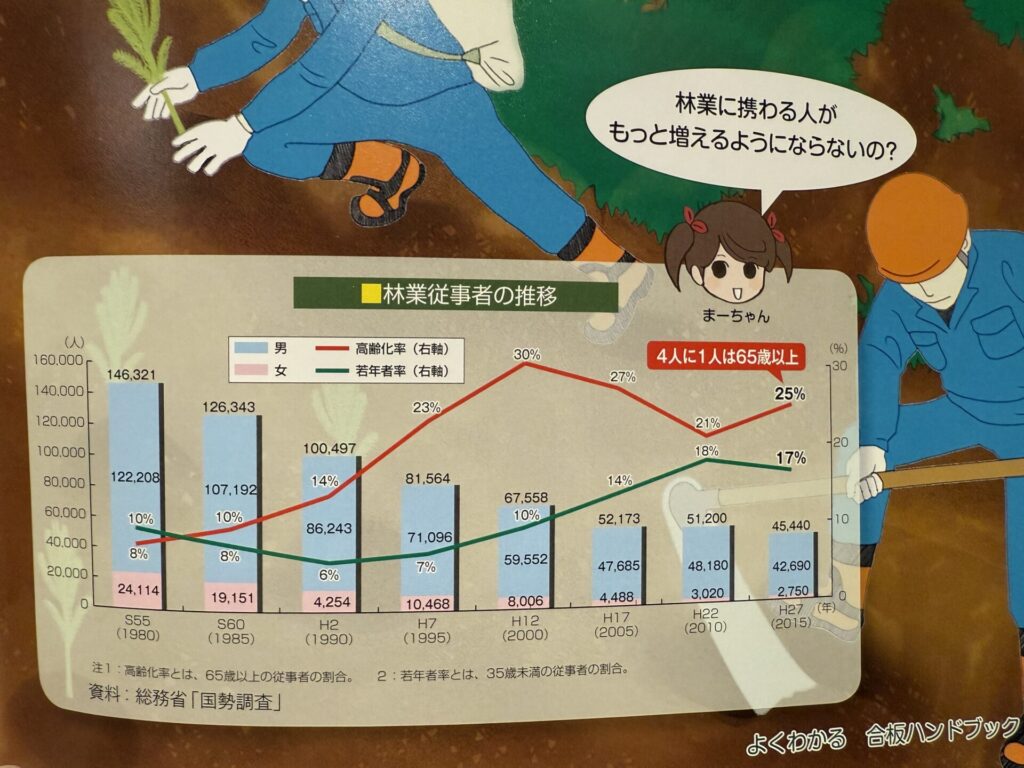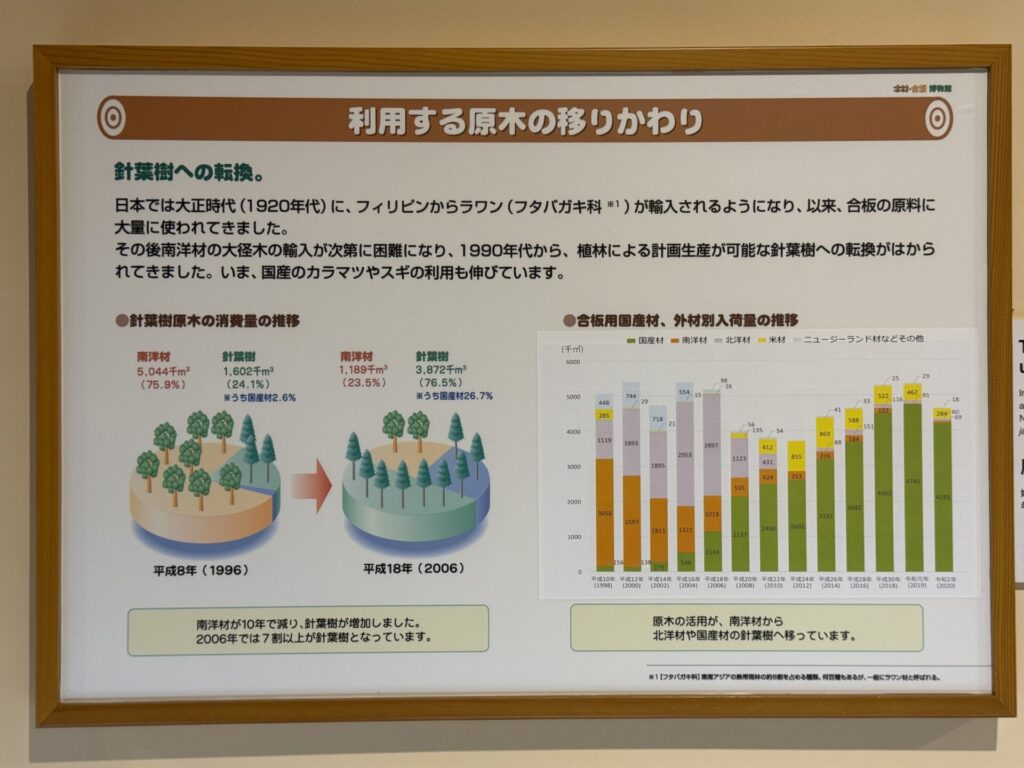モチオカ(望岡 慶)
なぜ日本の林業は衰退したのか
外材に押され、構造的に競争力を失った結果、林業が立ちゆかなくなった。
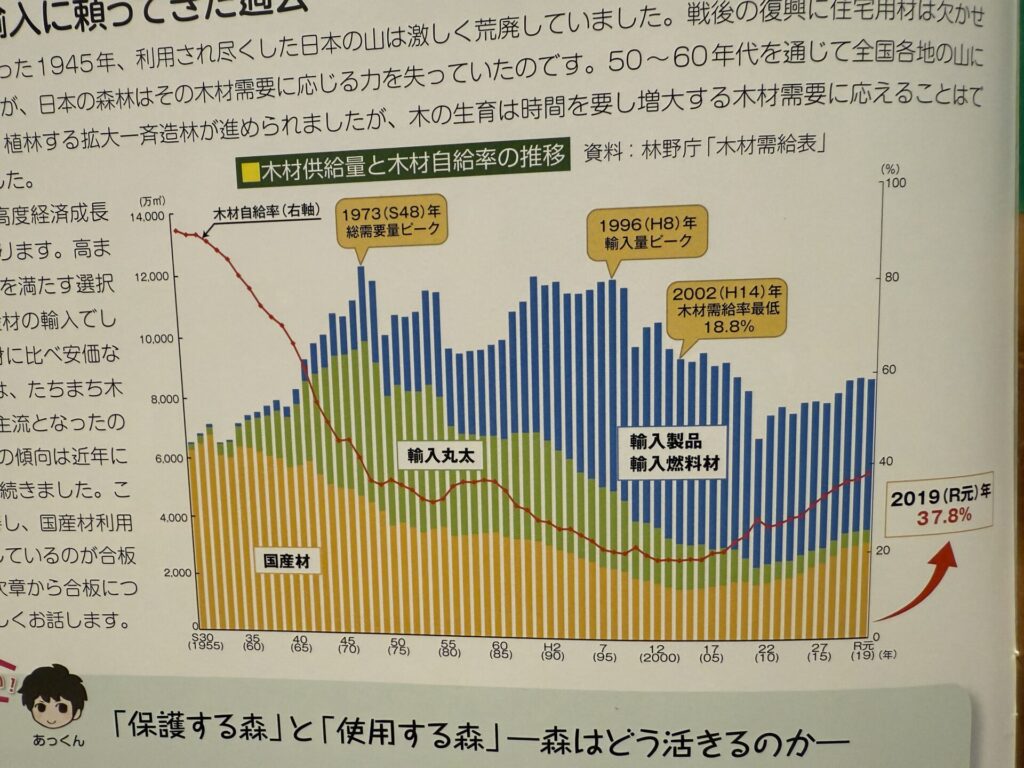 木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)
木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)
① 戦時中の森林資源の大幅な減少
- 戦争遂行のため、木材が軍需物資として大量に伐採された。
- 戦後も復興需要で伐採が続き、森林は大きく荒廃した。
- 木は育つのに時間がかかるため、国産の木材では需要に応えることができなくなり、外国産材の輸入が始まった。
※1960年代から木材輸入が完全自由化
② 円高による外材輸入の増大
- 1970年代の変動相場制導入、1985年のプラザ合意による円高で、外国産の木材が格安に。
- 国内木材ではコスト競争に勝てず、外材依存が進行した。
③ 生活様式の変化による国産材の需要減少
- 洋風住宅の普及により、和室向けの高級材(スギ・ヒノキ)の需要が減少。
- 建築用木材も規格化・工業製品化が進み、無垢材へのこだわりが薄れた。
④ 林業が発達しにくい構造
- 森林所有者が細かく分かれており、大規模経営が難しい。
- 作業道整備や機械化も遅れ、低コスト生産が実現できず、競争力が低下した。
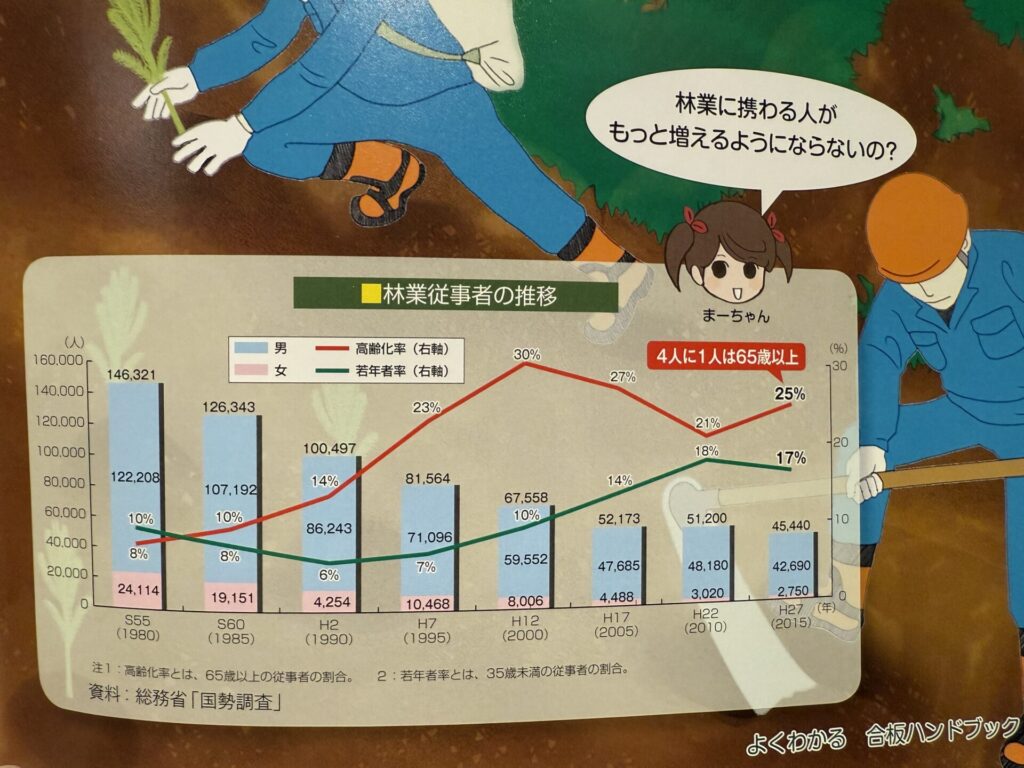 木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)
木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)
日本の木材輸入先
1970年頃:フィリピンから
1970年代後半〜:インドネシア、マレーシアから
↓
インドネシアで丸太の輸出規制→合板などに加工してから輸出
↓
1980年代後半〜:マレーシアから
↓
近年:カナダ、アメリカ合衆国、ロシアなどから(東南アジアからは合板での輸入が中心)
かつて日本で外材と言えば南洋材だった。東南アジアや南太平洋の熱帯ジャングルから伐り出された直径2メートルを超すような大木が大量に輸入された。
実は21世紀に入ると日本の南洋材輸入は激減して、木材需要の1割に満たず、丸太に限れば1%以下になっていた。
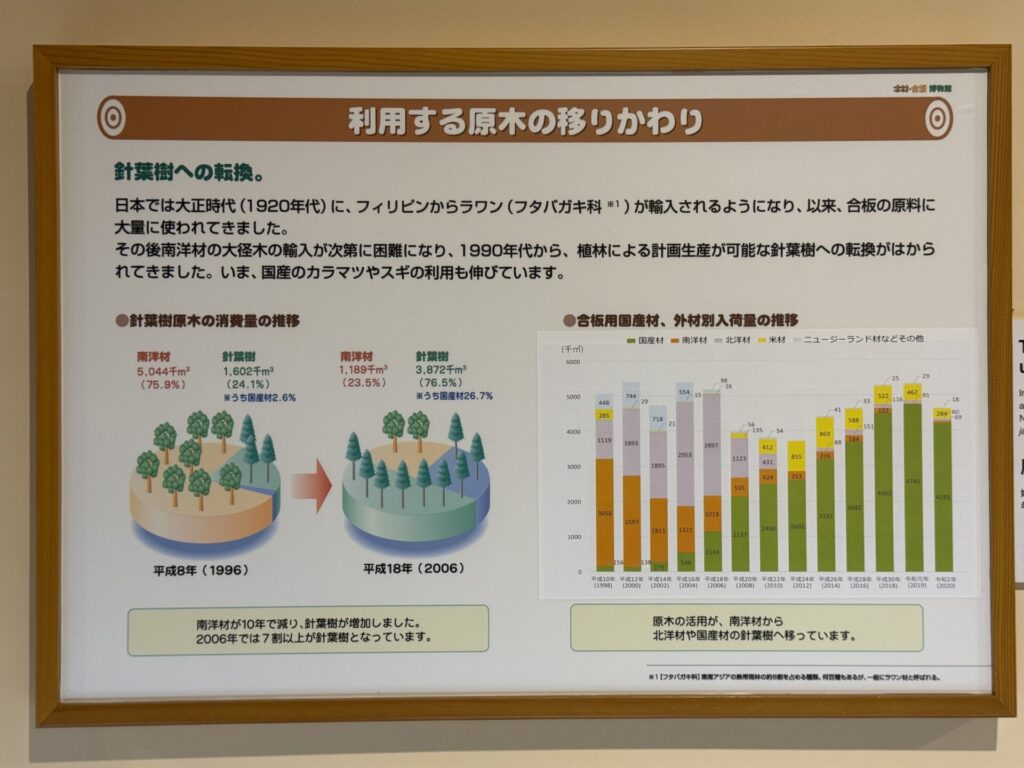 木材・合板博物館にて。(2025.4撮影)
木材・合板博物館にて。(2025.4撮影)
日本の林業の未来と課題