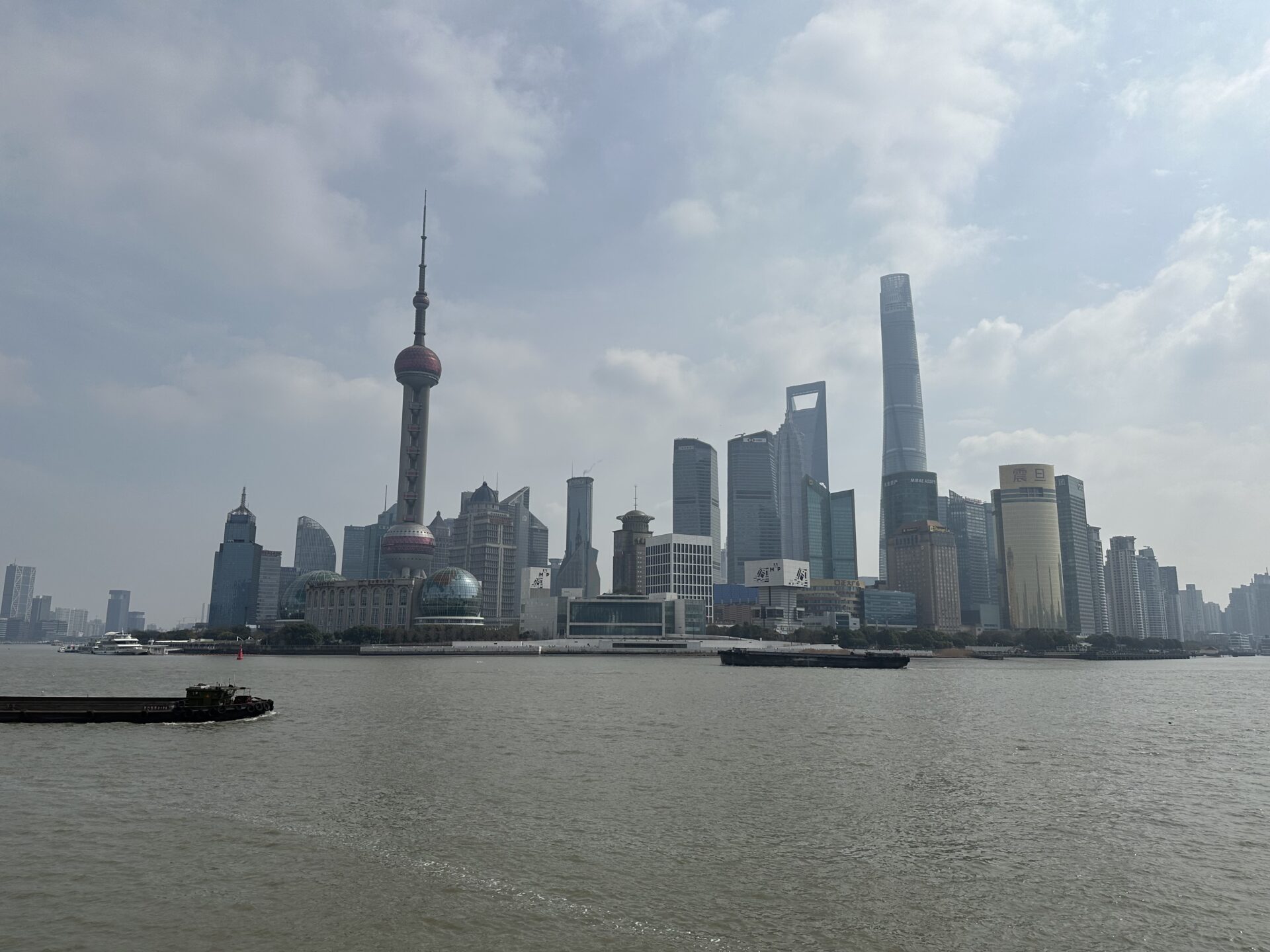南アジアの地形・気候をわかりやすく
南アジアという地域の本質は、「必死の生存競争が繰り広げられる”楽園”」ということ。
そして、その背景には地形と気候の特徴がある。
→「必死の生存競争が繰り広げられる”楽園”」という南アジアの本質を理解するために、地形と気候について学ぶ!

南アジアの地形

地形の大前提
- 山を越えるのはしんどい
- 平地なら、人やモノの移動がしやすい
この2つを基本にして、南アジアの山や平野を見ていく。


南アジアの山地
南アジアは北と東が山脈に囲まれている。
| ヒマラヤ山脈 | |
| カラコルム山脈 | |
| ヒンドゥークシュ山脈 | |
| パトカイ山脈・アラカン山脈 | |
| 西ガーツ山脈 | |
| 東ガーツ山脈 | |
| デカン高原 | |
| パミール高原 | 世界の屋根。パミール高原に向かってテンシャン山脈、クンルン山脈、カラコルム山脈、ヒマラヤ山脈、ヒンドゥークシュ山脈が伸びる。 |
| チベット高原 |


南アジアの平野
| ヒンドスタン平原 | ガンジス川、インダス川、ブラマプトラ川が運搬した土砂が堆積して形成された沖積平野。 |
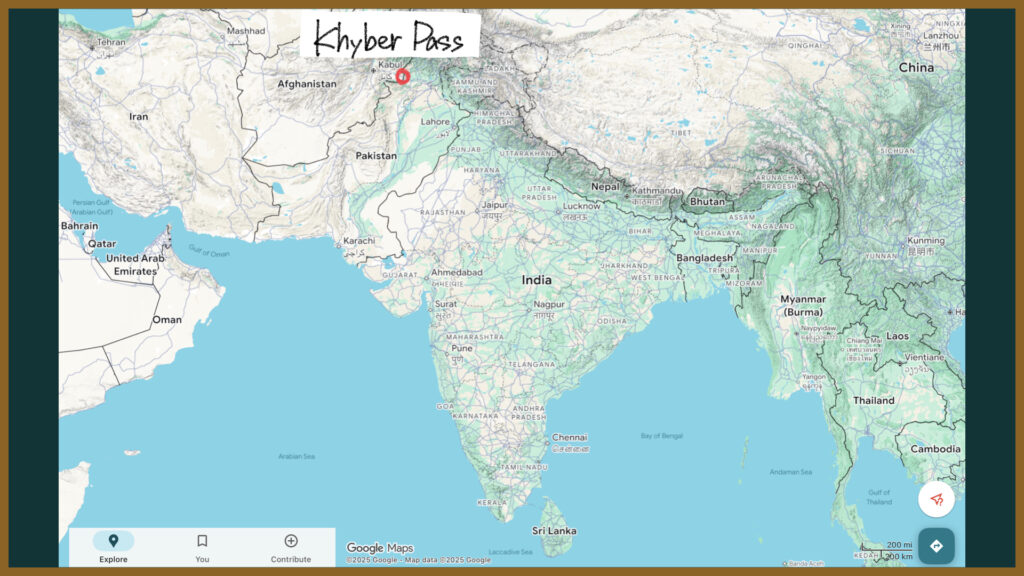
南アジアの河川
| インダス川 | |
| ガンジス川 | |
| ブラマプトラ川 |
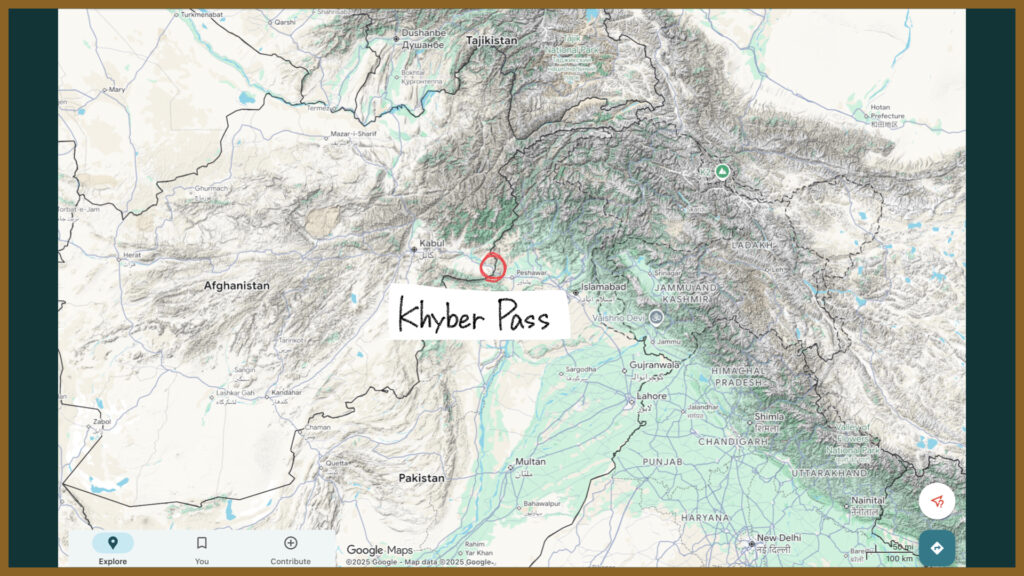
※インド洋から吹き付ける南西モンスーンは、主にヒマラヤ山脈にぶつかることで上昇気流となり、大量の雨をインドのガンジス川流域にもたらす。
南アジアの砂漠
| 大インド砂漠(タール砂漠) |
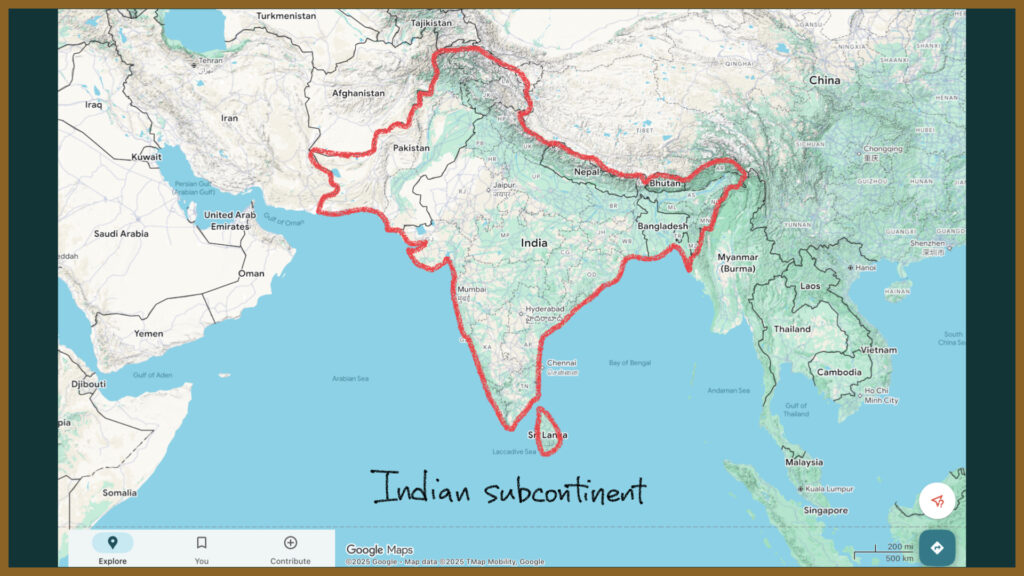
南アジアの海・島
| アラビア海 | |
| ベンガル湾 | |
| インド洋 | |
| モルディブ諸島 | |
| セイロン島 | |
| アンダマン諸島 | インド、ミャンマーに属する島々。 |


南アジアの気候
気候の大前提
温暖で雨が多い地域(農業がしやすい地域)は生活しやすく、人が集まりやすい。
南アジアの気候の仕組み
赤道にやや近い
南アジアは、赤道にやや近い場所に位置している。ゆえに気温が高く、蒸発量が多くなる。特に夏は顕著。

季節風(モンスーン)
インド亜大陸に対して、夏は南西からの風が、冬は北西からの風が吹く(季節風)。
この季節風は夏にアラビア海で蓄えた水蒸気をインドにもたらし、大量の降雨をもたらす。
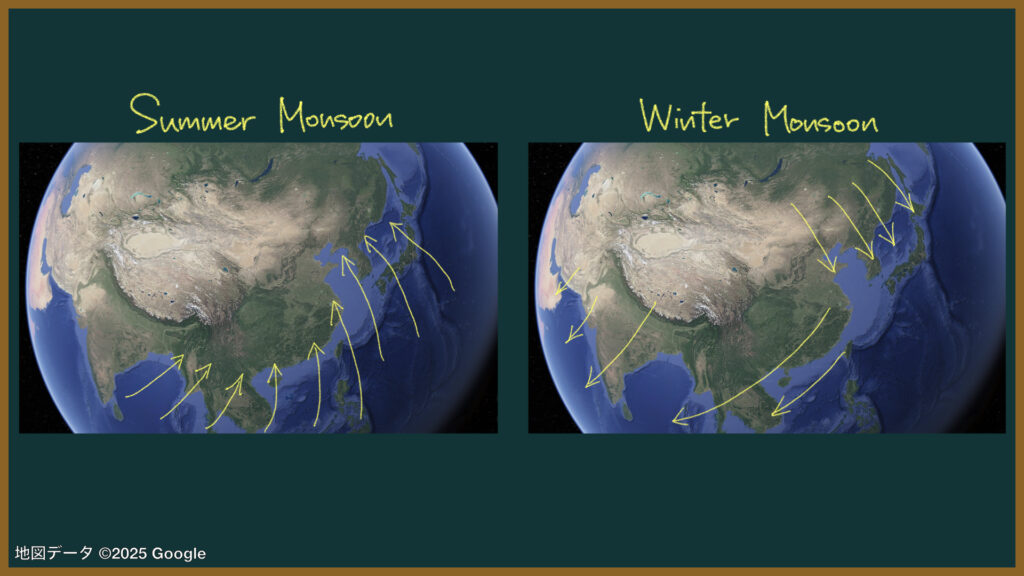
※緯度的には亜熱帯高圧帯の影響を受ける地域だが、季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。(→西アジアは季節風の影響を受けにくいため乾燥する)
中緯度高圧帯
南アジアの大部分は北緯20〜30度に位置する。
この緯度帯は中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)が広がるエリアで、下降気流が強いため雲ができにくく、雨が降りにくい。(→砂漠気候 BW、ステップ気候 BS)
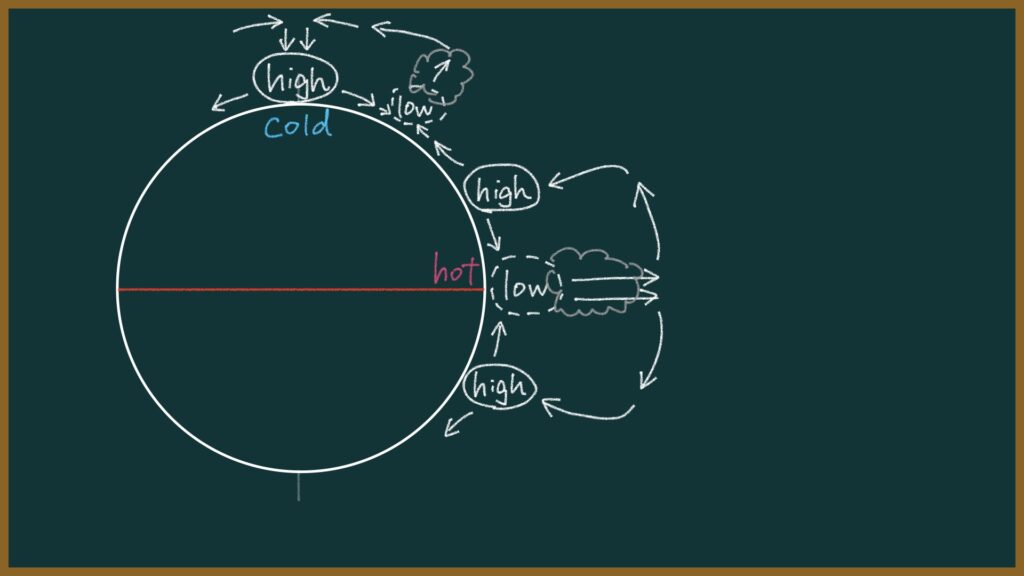
関連:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】
地域ごとの気候
南アジアの気候は、主に
- 赤道にやや近い
- 季節風(モンスーン)
- 中緯度高圧帯
という3つの要素が組み合わさって決まる。
その結果、地域ごとにさまざまな気候が見られる。

| インドの全体像 | インドの気候は多様だが、全体的に温暖。モンスーンの影響で雨季と乾季がはっきり分かれている地域が多い。 |
| デカン高原 | やや乾燥している。西ガーツ山脈と東ガーツ山脈に囲まれていて、雨陰になりやすいから。 |
| インド北東部(アッサム地方) | 季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。 |
| インド南西岸(西ガーツ山脈の風上側) | 季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。 |
| インド北西部・パキスタン | 砂漠気候(BW)、ステップ気候(BS):緯度的に亜熱帯高圧帯の影響を受ける地域であり、降雨をもたらす上昇気流を起こす地形が近くにない(西ガーツ山脈のような山脈がない)。夏に湿った季節風が吹いても、そこまで雨が降らないため、蒸発量が上回ってしまう。 |
重要ポイント
東西南北を自然の「壁」に囲まれている
南アジアは、北はヒマラヤ山脈、東はパトカイ山脈、西は砂漠、南は海に囲まれた地域。

インドとミャンマーの間にある山岳地帯は、陸路での移動を困難にし、インドから東南アジアへの影響を限定的なものにしていたはず。
→だからこそヒンドゥー教はインドより東には広まらなかったし、「南アジア」と「東南アジア」の区分けができた。
自然豊かで定住しやすい場所
ヒマラヤ山脈という険しい山脈があり、モンスーン地帯で降水量が多いため、大河川が流れる。
- インダス川
- ガンジス川
- ブラマプトラ川
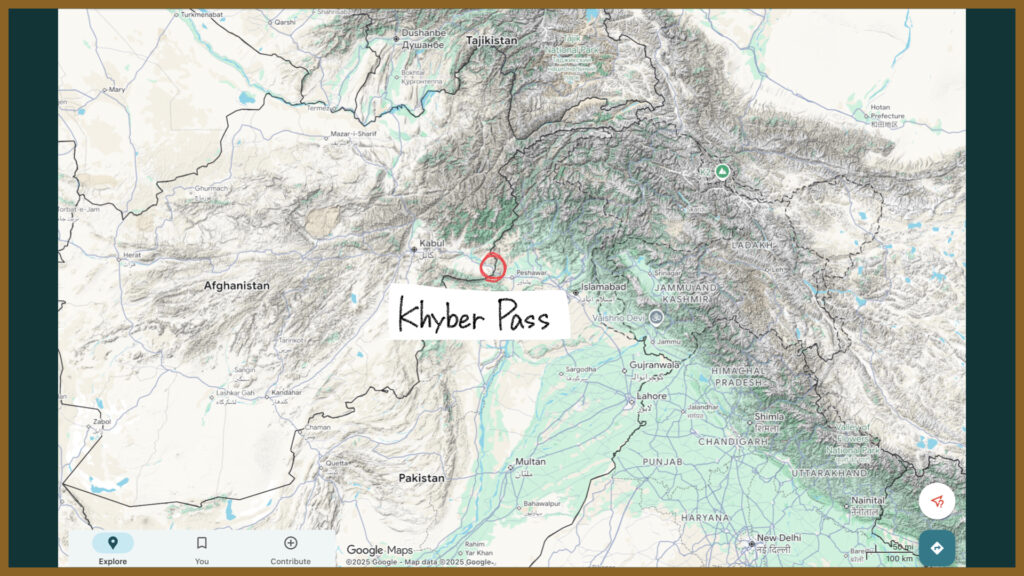
特にヒンドスタン平原は、水資源が豊富な大農業地帯。定住する上で魅力的な場所だった。
だからこそ工業が発展した現代においては、ヒンドスタン平原あたりは貧しい地域になっているのだけれど。。
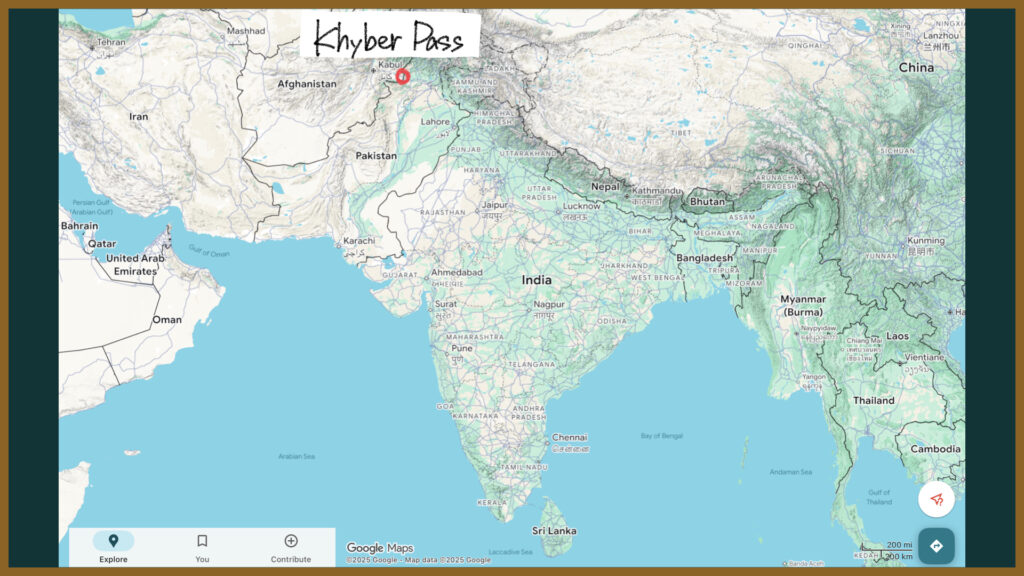
しかし過酷
南アジアのすべてが恵まれた土地というわけではない。
| インド北西部のパンジャーブ地方 | 小麦栽培が盛んな穀倉地帯。 |
| 西部(パキスタン側) | 砂漠が広がる。 |
| ガンジス川流域 | ガンジス川は流量の季節変動が大きく、灌漑設備の整備が難しい。稲作地帯だが、安定した暮らしには向かない。(実際、ガンジス川流域は貧困層が集中する地域のひとつになっている) |
| ガンジス川下流域(バングラデシュ) | サイクロンや洪水といった自然災害が頻発する、極めて過酷な土地。(ここに南アジアにおける「少数派」のイスラム教徒が集まったのは偶然ではないだろう) |
| デカン高原(南インド) | レグール土という土壌が分布するが、この土は腐植(落ち葉などの有機物)をあまり含まないため、腐植を好む小麦のような作物にはそれほど向かない。台地状の地形のため灌漑も難しく、稲作にも限界がある。(だからこそデカン高原では綿花栽培が行われている) |
こうして見ていくと、人々が安全に安定して暮らせる地域は限られている。大多数の人々は過酷な環境の中で生き延びなければならない。
しかも、南アジアの夏は高温多湿。食べ物は腐りやすい。(だからこそスパイスを使って食材を煮込むカレー文化が発達したのだろう)
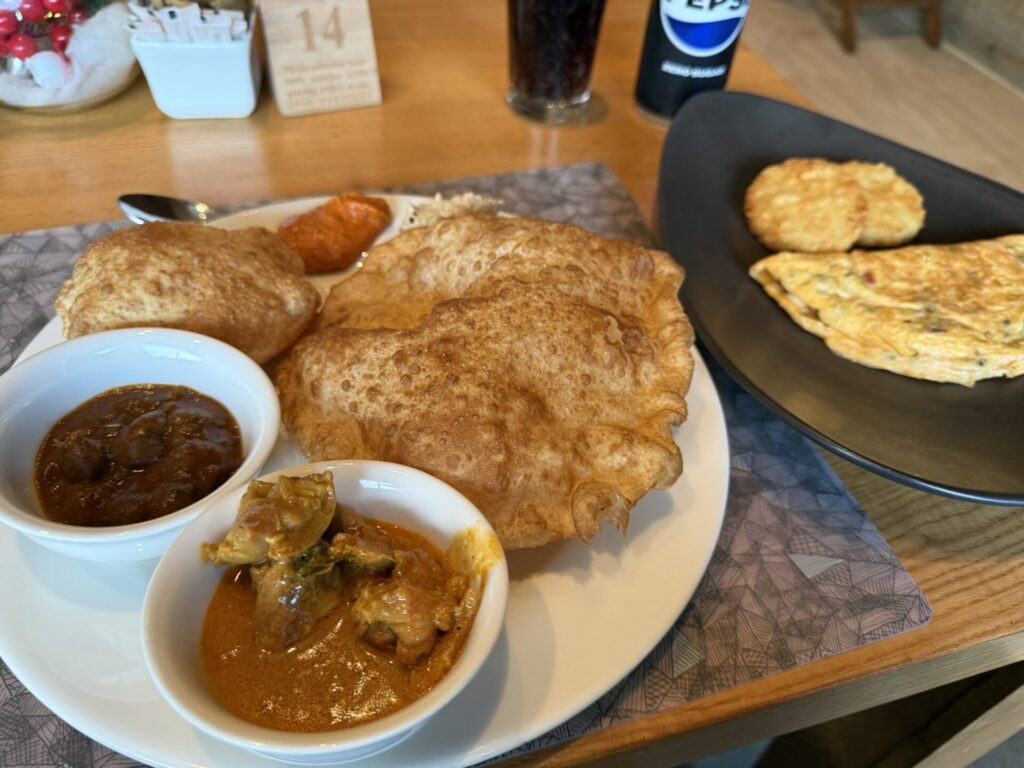
インド社会の中での下位グループは生活しにくい場所に追いやられた。
- 先住民→デカン高原に
- イスラム教徒→パキスタンとバングラデシュに
インドの気候は多様
気候が多様(かつ地形も多様)だからこそ、インドは様々な農作物を生産できる。
高温な地域も多いので、スパイス栽培にも適している。
インド洋に突き出している
アラビア海とベンガル湾を隔てる形で、インド亜大陸はインド洋に突き出ている。
それゆえに、インドはアフリカ・中東・東南アジアを結ぶ海上交通の要所として機能してきた。