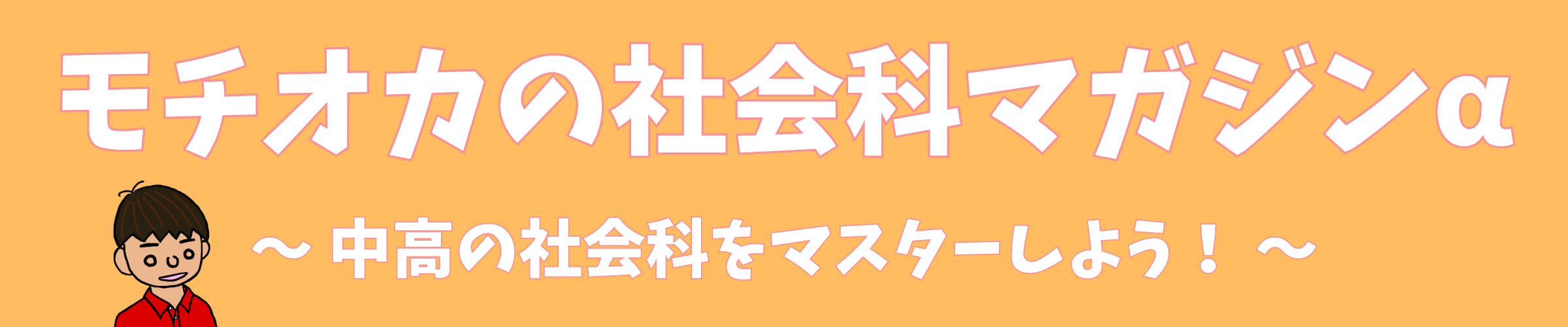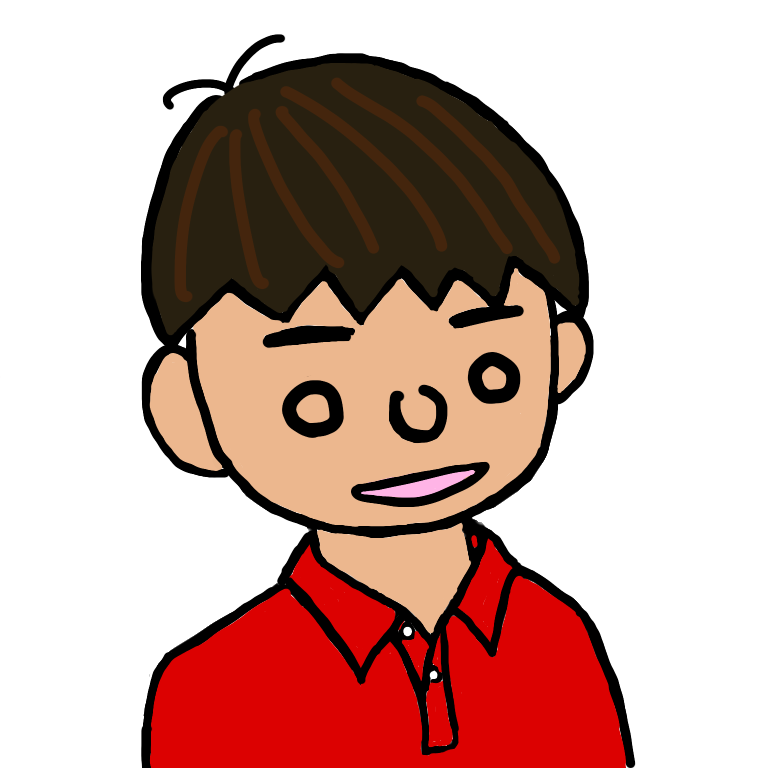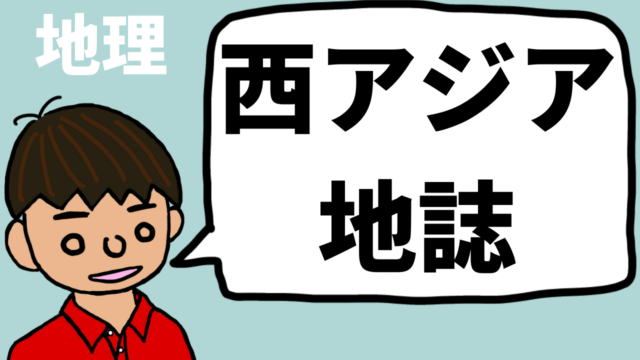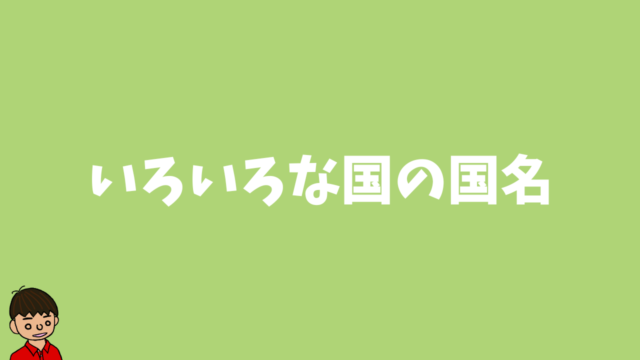広がる境界・狭まる境界・ずれる境界とは?東大卒元社会科教員がわかりやすく解説
望岡 慶(Kei Mochioka)
/
本記事の内容
- 広がる境界
- 狭まる境界
- ずれる境界
プレートの境目(境界)
プレートの動き方は3通り
| 2枚のプレートが離れる | =広がる境界 |
|---|---|
| 2枚のプレートが近づく | =狭まる境界 |
| 2枚のプレートがずれる | =ずれる境界 |
※この言葉自体は覚えなくてOK!「プレートの境界で3通りの動き方があるんだ!」ってことをつかむことが大事!
広がる境界のポイント
・マントルの上昇部に相当する
→地下からマグマが供給されて、プレートが左右に押し分けられる
・広がる境界のほとんどが深海底に存在する
→開いた割れ目には、地下からマグマが供給され、新しく地殻が作られる
→盛り上がっていて、海嶺と呼ばれる
(例)大西洋中央海嶺
・まれに陸上にも存在する
(例)アフリカ大地溝帯、アイスランド(大西洋中央海嶺が陸上に現れたのがアイスランド島)
→開いた割れ目のことを地溝と呼ぶ
狭まる境界のポイント
・プレート同士が近づくところ
・プレートには比重が重い海洋プレートと比重が軽い大陸プレートがある
→近づくプレートの違いから、狭まる境界は2パターンに分かれる(→沈み込み型・衝突型)
沈み込み型
・大陸プレートと海洋プレートの衝突
・比重が重い海洋プレートが沈み込む
→沈み込んだ海洋プレートと大陸プレートの境界に溝(海溝)ができる
(例)日本海溝
・地震が起きやすい
・沈み込む時に岩石が溶けてマグマが発生し、多くの火山ができる(→火山列)
衝突型
・比重が軽い大陸プレート同士の衝突
→沈み込みが起こらず、境界が盛り上がる
→大山脈が形成される
(例)ヒマラヤ山脈やチベット高原(←インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの衝突)
ずれる境界のポイント
(例)サンアンドレアス断層(アメリカ西部)、北アナトリア断層 (トルコ)
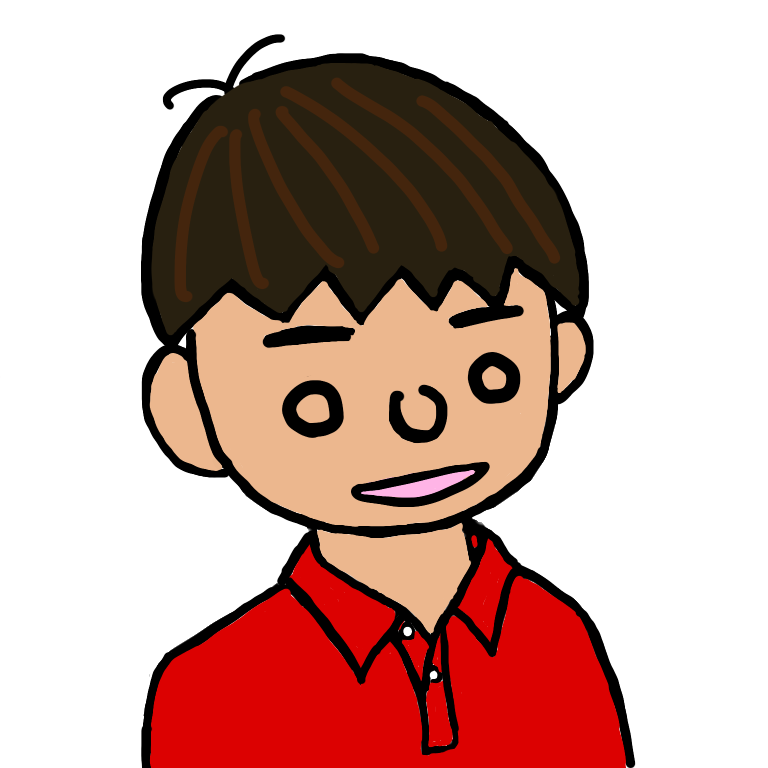
望岡 慶
最後までお読みいただきありがとうございました!
地理の記事・動画一覧はこちら
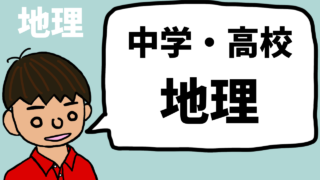
中学・高校地理まとめサイト【東大卒元社会科教員がわかりやすく解説】
地理に関する記事のカテゴリです。地理について解説した記事を一覧にしてまとめました。
教員向け:社会科の教材研究用のサイト...

地理を解説したYouTube動画まとめ【わかりやすい】本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルを運営しています!...
参考文献
通信教育
学習漫画・参考書
社会科チャンネル
社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。