多数派が正しくて、少数派が間違ってるのか?
モチオカ(望岡 慶)
モチオカの社会科プラス

かつては、遠くの海まで大型の船で魚をとりに行く遠洋漁業が盛んだった。
しかし現代では、遠洋漁業や沖合漁業は世界的に衰退傾向にある。
なぜなら、とにかくコストが高いから。
そのうえ、世界的に「魚をとりすぎてはいけない=乱獲の防止」という意識が高まってきている。
そのため各国では、沿岸の資源をきちんと管理し、決められた漁獲枠の範囲でとるというスタイルが主流になりつつある。
遠洋漁業:遠隔の漁場に出て行う漁業。
沖合漁業:200海里内の排他的経済水域において2週間以内で行われる漁業。
沿岸漁業:その国の領海内で行われる漁業。
栽培漁業:人工的に孵化させた稚魚を海などに放流し、成長した後に捕獲する漁業。
養殖業:排卵から漁獲まですべて人工的に管理して行う漁業。
現在、最も注目されているのが養殖。
自然の海で魚をとる「漁業」と違い、人間が魚を育てて出荷する養殖は、
といったメリットがある。
そのため、世界の水産物の半分以上はすでに養殖由来になっており、今後ますますその割合は増えていくと見られている。
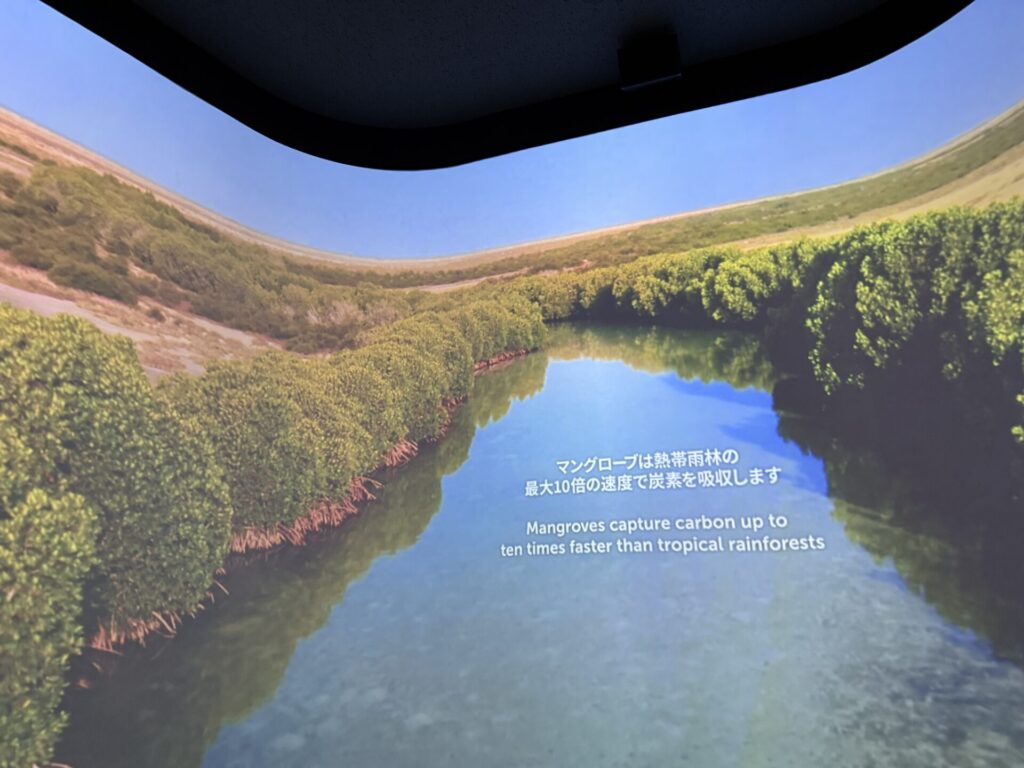
→ タイ・インドネシア・フィリピンなどで深刻な問題に
参考:魚粉の国内価格が最高 養殖業、エサ不足で経営打撃(日本経済新聞)