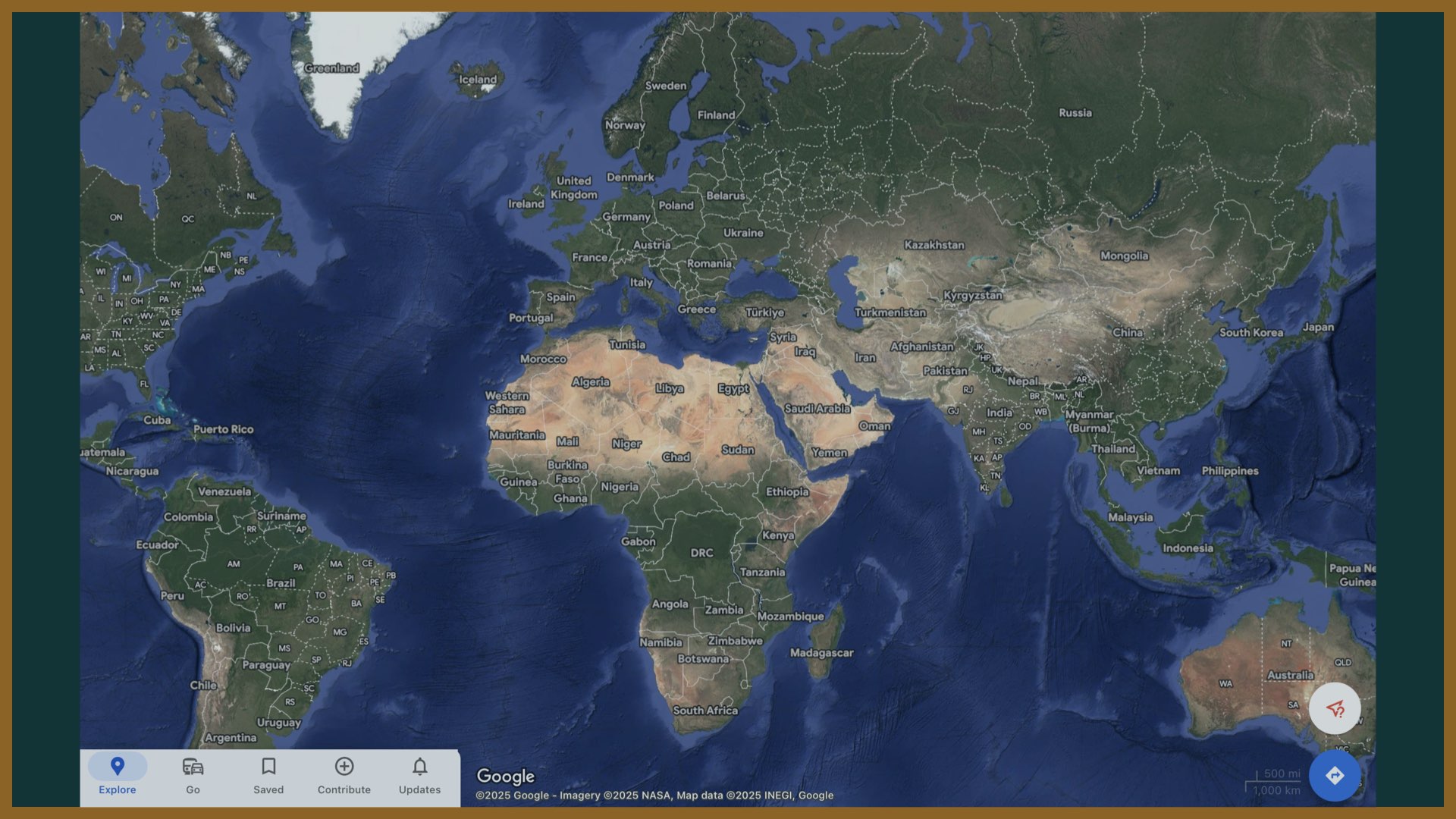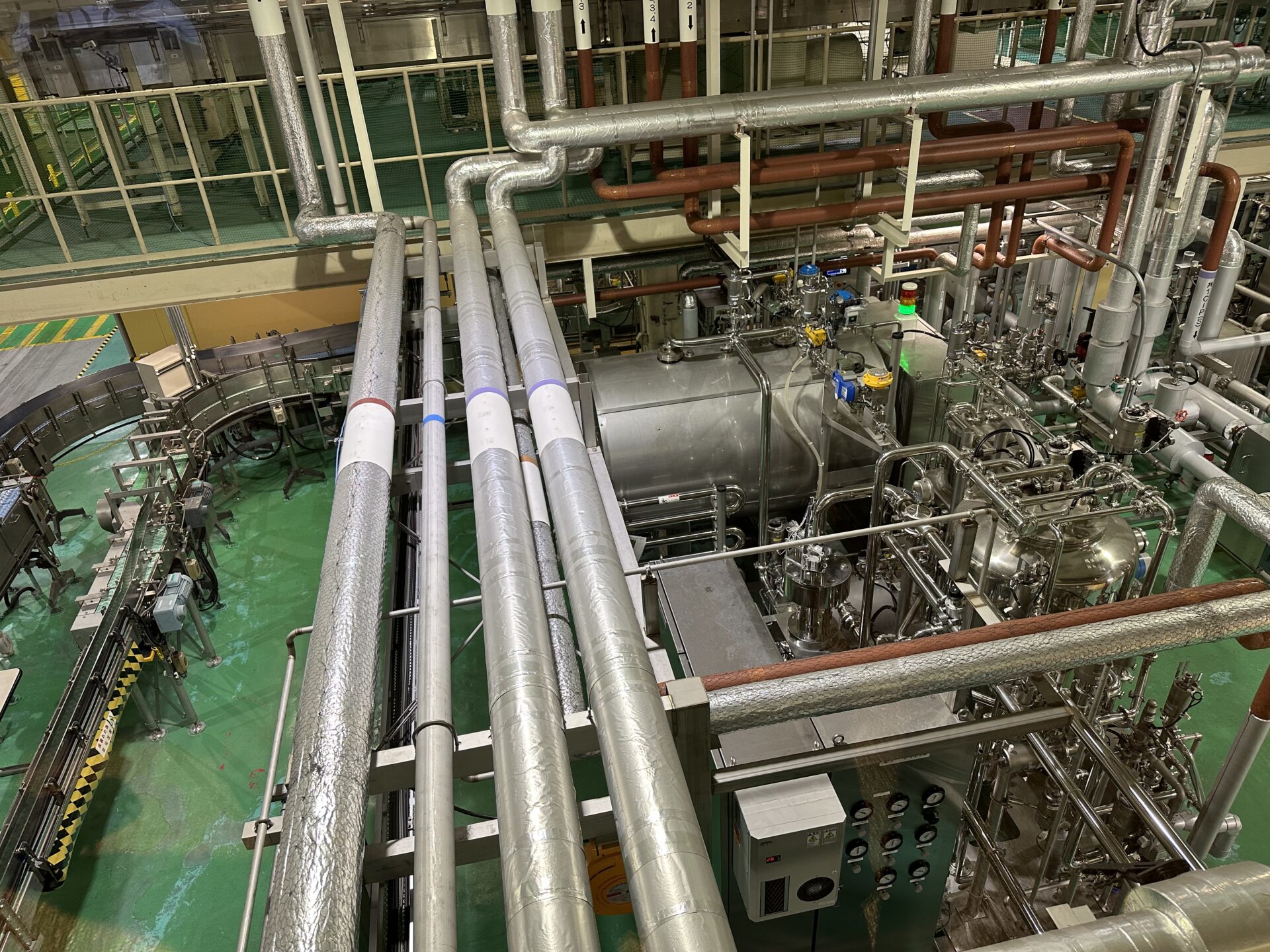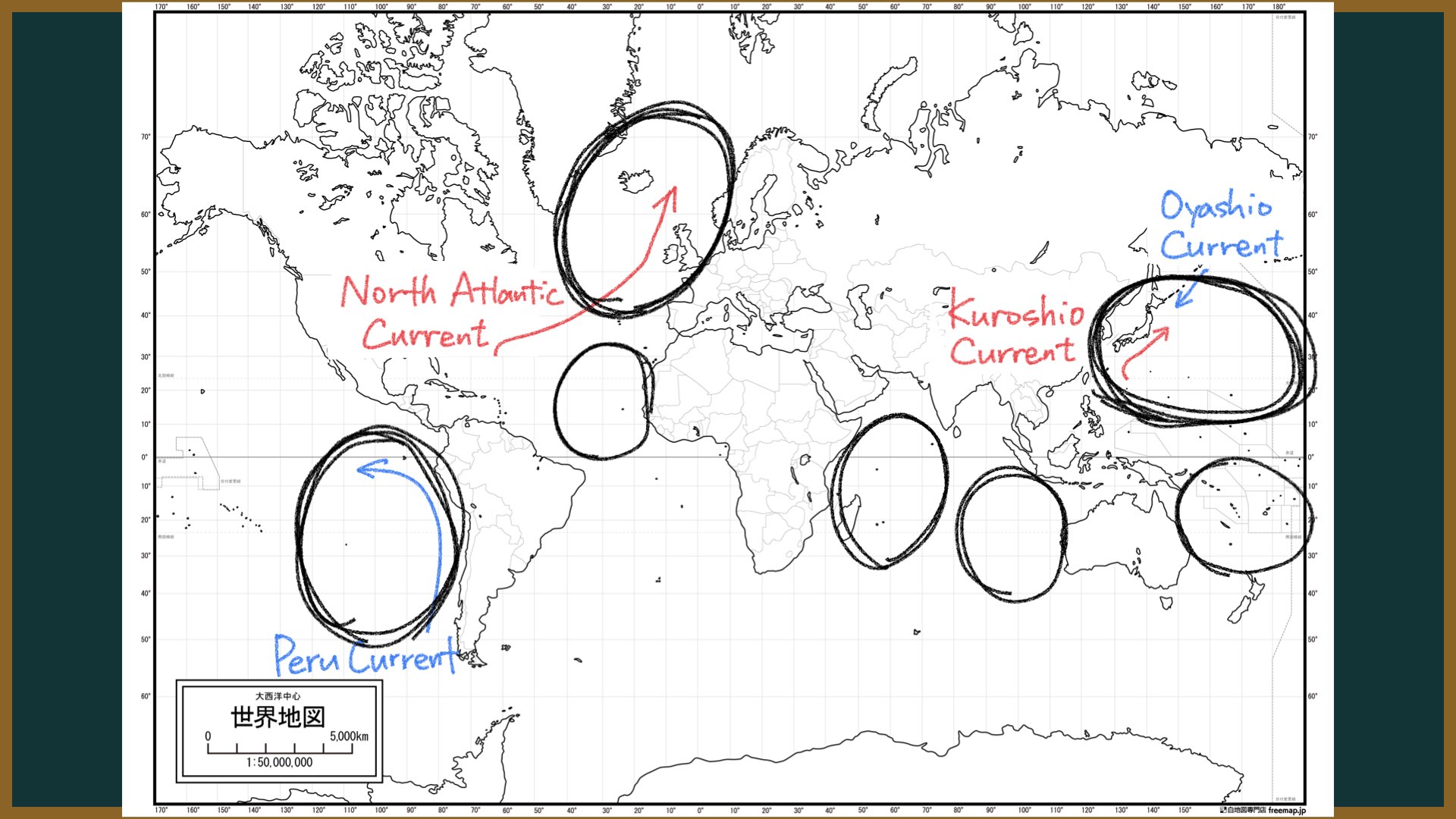日本のコメ農家は儲からないのか?
「日本のコメ農家は儲からない」と言われることがあるが、それは本当なのか?
同じ農業でも、畑作や酪農、畜産では事情が違うのだろうか?
稲作

機械化が進んでいる
稲作は、年間を通じた作業量が少なく、田植えや収穫の時期に集中して労働が発生するという特徴がある。
耕うん・田植え・収穫・乾燥などの工程はすでに機械化が進んでおり、省力化という点では他の作物に比べて優れている。
価格を決めにくく、儲けにくい
一方で、米の多くは農協や集荷業者にまとめて出荷されるため、価格は市場で決まるのが一般的。農家が自由に価格を決めることは難しく、販売単価は比較的低い傾向にある。
ブランド米として個人で販売することも可能ですが、米は重く、輸送コストが高いため収益性はあまり上がらない。
畑作(野菜・果樹など)

手作業が多く、労働集約的
畑作は野菜や果樹など作物の種類が多く、それぞれに応じた細かい管理や収穫作業が求められる。
雑草の手入れ、病害虫対策、収穫や選別、袋詰めなど、多くの工程が手作業で行われるため、労働量は非常に多くなる。
それゆえ、収益性を上げるには低賃金労働力を活用することが重要になる。
ブランディング・直販の余地が大きい
一方で、販路を工夫すれば農家自身が価格を設定できる場合もあり、直販やブランド化に成功すれば高収益も期待できる。
とくに近年はインターネット販売や農家の直営店舗など、販売の自由度が広がっており、稲作に比べて価格決定権を持ちやすい作目だと言える。
酪農(乳牛)

365日稼働だが、機械化が進んでいる
酪農は牛の世話と搾乳が毎日必要で、年間を通じて休みがない。
労働時間は長いものの、近年では搾乳ロボットや自動給餌装置など省力化技術が導入されつつあり、大規模経営では作業の負担を軽減できるようになってきた。
価格は決められないが、安定性は高い
搾った牛乳は毎日出荷されるため、収入は比較的安定している。
ただし、価格はほぼ固定されており、酪農家が自由に値段を設定することはほとんどできない。乳業団体や政府との調整によって乳価が決まるため、ブランド化によって高く売るような自由度は小さいと言える。
畜産(肉牛・豚・鶏)

手間はかかるが、工夫次第で省力化も可能
畜産では、日々のエサやりや健康管理、清掃などの作業が必要で、労働量は多め。
ただし、設備の自動化やICTの導入が進んでおり、一定の規模があれば省力化は可能。
とはいえ、病気の管理や出産・育成には人の手が必要で、完全な省力化は難しい面もある。
ブランディング・直販の余地が大きい
畜産では、和牛や銘柄豚などブランド化によって高価格で取引される例が多く、販売先によっては農家が価格を設定することも可能。契約出荷や飲食店への直接販売などを通じて、比較的自由な価格設定ができる点は大きな強み。
ただし、初期投資が大きく、病気による損害も深刻なため、リスクとリターンがともに大きい分野と言える。
コメと牛乳はコモディティ化しやすい
「コメ」と「牛乳」は見た目や味の違いが分かりにくく、他の商品との差が伝えにくいため、コモディティ(代替可能な汎用品)として扱われやすい。
その結果、価格競争に巻き込まれやすく、安く買い叩かれがち。
| コメ | 牛乳 | |
|---|---|---|
| 見た目 | どれも白く、品種の違いが分かりにくい | 全て白く、パッケージでしか差が出ない |
| 味の違いの伝えにくさ | 品種ごとの味の違いを体感しにくい(特に外食では) | 乳脂肪分などの違いはあるが、一般消費者は意識しにくい |
| 日常性・定番感 | 毎日食べる/買う=“とりあえず安ければいい”という判断になりがち | 毎日飲む家庭も多く、安さ重視になりやすい |
| 流通構造 | 農協や集荷業者が価格決定→農家は価格を決められない | 乳業メーカーや指定団体が価格決定→酪農家も受け身 |
一方、畑作・畜産は…
| 作目 | 特徴 |
|---|---|
| 畑作(野菜・果物) | 色・形・香り・甘さ・有機栽培など、違いが“見える・感じられる” |
| 畜産(肉) | 和牛・銘柄豚・鶏卵の黄身の色など、違いを伝えやすく、ブランド化しやすい |