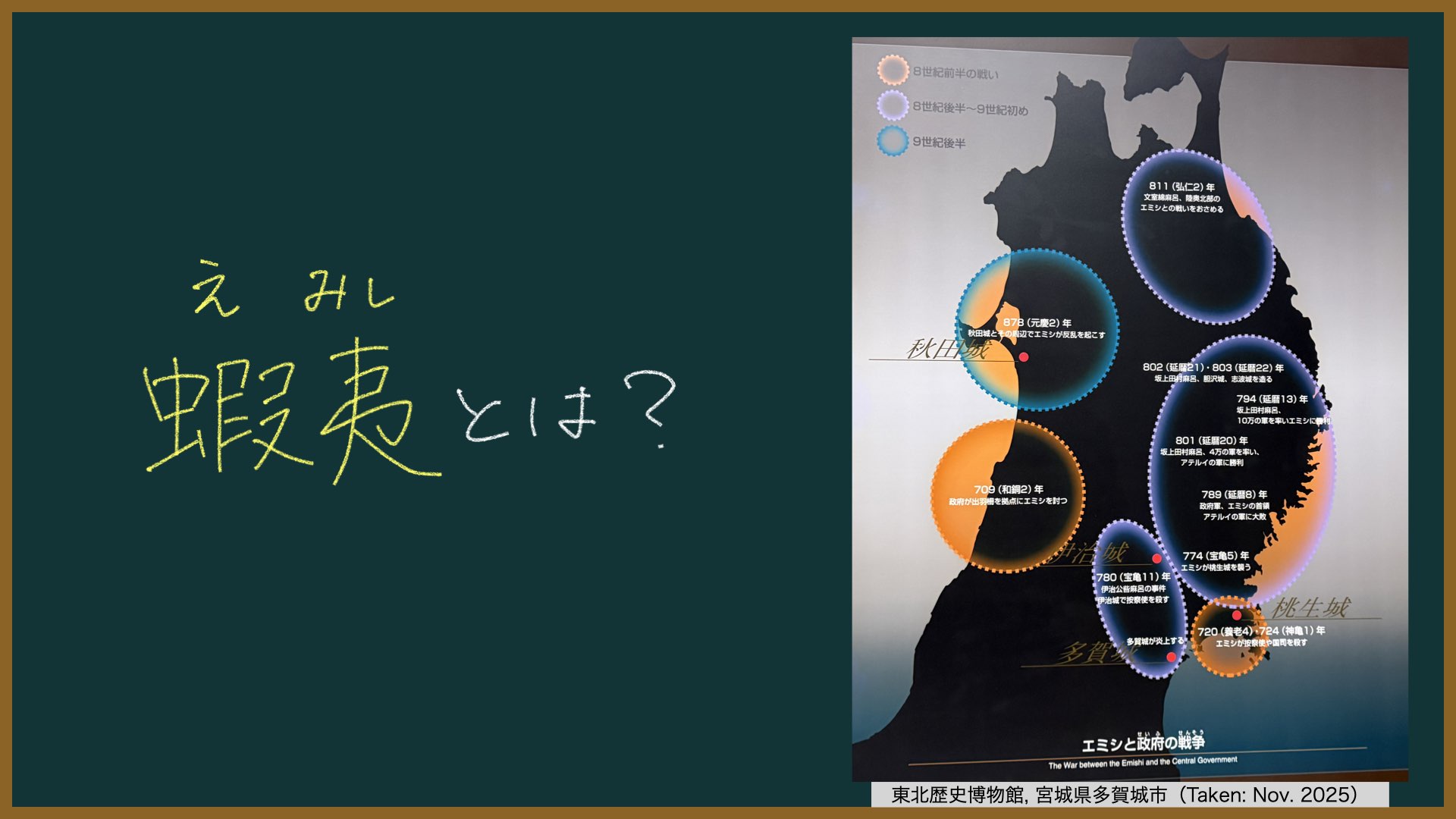なぜ「北海道牛乳」とわざわざ言うのか?

スーパーやコンビニで見かける「北海道牛乳」。
なぜわざわざ「北海道」と強調されるのか?
飲用牛乳は都市の近くでつくられる

牛から搾ったままの生乳は、日持ちしない上に重い。冷蔵が必要で、遠くまで運ぶと時間もコストもかかる。
だから、「そのまま飲む用の牛乳(=飲用牛乳)」は、東京・大阪などの都市の近くで作る方が合理的。
千葉・群馬・栃木など、関東圏の酪農地帯がその代表。
北海道の酪農
一方で、北海道の酪農は圧倒的なスケールと効率のよさが特徴。
- 土地が広く、大規模な牧場がつくれる
- 気候が冷涼で、牛にとっても過ごしやすい
- 飼料作物(とうもろこしや牧草)も自前で生産できる
つまり、コストを抑えて高品質な生乳を大量生産できるという、酪農に理想的な条件がそろっているのが北海道。
飲用牛乳としては不利
しかし、ここでひとつ問題がある。
それは北海道は都市から遠すぎる、ということ。
生乳のまま本州に大量に運ぶのは大変。だから多くは、飲用ではなく加工用に回される。
よって「乳製品への加工」が主流

北海道で生産された生乳の多くは、バター・チーズ・脱脂粉乳などに加工されてから本州や海外へ運ばれる。
加工すれば、長持ちするし、輸送もしやすくなるから。
北海道は、日本の「乳製品の供給基地」としての役割を担っている。
でも、外国と戦うのは厳しい
ただし、世界にはもっと強い国もある。
特に強いのはニュージーランドやオーストラリア。放牧中心で低コスト。こうした国々の乳製品は、値段がとても安く、大量に輸出されてくる。

日本の乳製品は、人件費もエサ代も高いため、価格面では勝てない。
→【ニュージーランド】なぜ乳製品の輸出が盛ん?(輸送費が高いはずなのに)
手厚い保護が必要になる
そこで日本は、国の制度で国産酪農を守っている。
- バターは国家が輸入量を管理し、一部は関税で守る
- 脱脂粉乳は国家が備蓄・買い取り
- 酪農家には生乳価格の安定制度や補填金が支給される
つまり、北海道の酪農は「保護が前提の産業」である。

だからこそ「北海道牛乳」と言う
北海道の酪農は、コスト面では外国に勝てないが品質は高い。
そこで登場したのが「北海道ブランド」。
「広大な自然の中で育った牛からしぼった、濃厚でおいしい牛乳(を使った商品)」というイメージを全面に押し出して勝負している。
実際、、「北海道牛乳」や「北海道バター」「北海道ソフトクリーム」などが人気商品として定着している。