ヨーロッパの地形と気候をわかりやすく:用語の丸暗記にならないために
ヨーロッパという地域の本質は、「異なる人々が出会い、衝突が起きやすい場所である」ということ。
そして、その背景には地形と気候の特徴がある。
→「異なる人々が出会い、衝突が起きやすい」というヨーロッパの本質を理解するために、地形と気候について学ぶ!

ヨーロッパの地形
地形の大前提
- 山を越えるのはしんどい
- 平地なら、人やモノの移動がしやすい
この2つを基本にして、ヨーロッパの山や平野を見ていく。


ヨーロッパの山脈

特におさえておきたい4つの山脈
| アルプス山脈 | 中央ヨーロッパに横たわる大山脈。南北の移動を妨げる自然の壁になってきた。 |
| ピレネー山脈 | フランスとスペインの間にある。ここも南北の移動を妨げ、イベリア半島(スペイン・ポルトガル)が独自の文化を持つ背景になった。 |
| カルパティア山脈 | 中欧〜東欧にかけて弧を描くように広がる山脈。山々に囲まれたパンノニア平原(ハンガリーなど)が形成され、文化や言語の独自性が保たれてきた。 |
| ディナル・アルプス山脈 | バルカン半島に広がる山地。複雑な地形が小さな谷や盆地をつくり、そこに異なる民族が暮らしてきた。バルカンの複雑な歴史は、この地形と無関係ではない。 |

その他の特徴的な山脈
| スカンディナヴィア山脈 | 氷河を発達させ、フィヨルドという独特な地形を生んだ。 |
| アペニン山脈 | イタリア半島を南北に縦断。交流を妨げた(→イタリアの統一を遅らせた?) |
| ペニン山脈 | イングランドの中央部を南北に走る。東西交通の分断が、工業地帯や港の発展に影響を与えた。 |
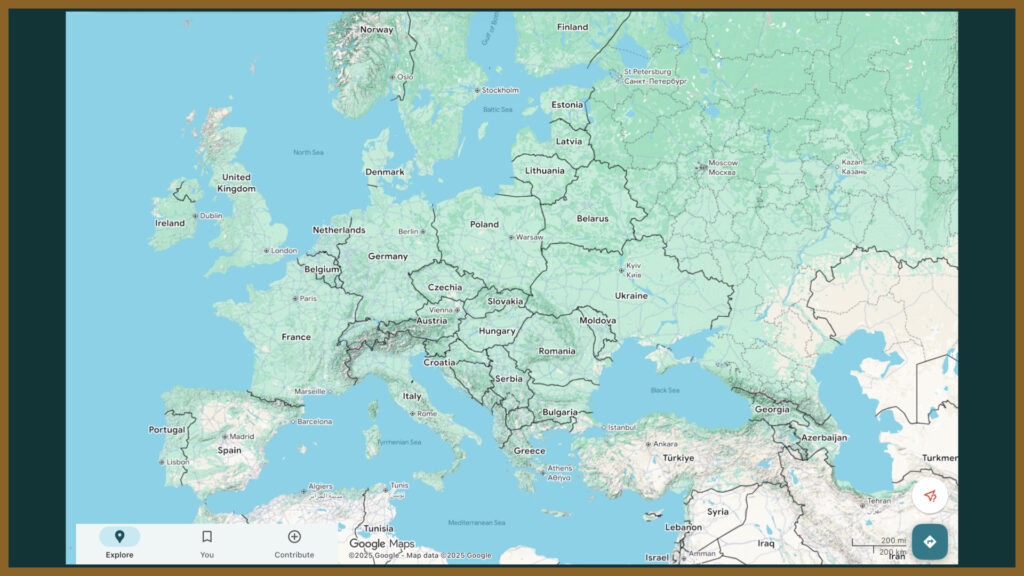
ちなみに、以下のことも結構大事だと思う。
- フランスは南東部に山がちょこっとあるくらいで、全体的にかなり起伏が小さい。
- ドイツは中部から南部がややゴツゴツしている。チェコとの国境には山がある(っていうか、山があるからそこにチェコとの国境が引かれた)。
- スペイン(イベリア半島)は全体的にゴツゴツしている。

ヨーロッパの平野
| 北ドイツ平原・フランス平原 | 西ヨーロッパの北部に広がる平野。大きな障害物がなく、移動がしやすい。だからこそ争いも起きやすかった。 |
| 東ヨーロッパ平原 | ロシア〜ウクライナにかけて広がる。こちらも移動しやすく、歴史的には戦争や侵略の舞台になってきた。 |
| パンノニア平原 | アルプスとカルパティア山脈に囲まれた内陸の盆地。ハンガリーなどがここに含まれる。 |

- ルーマニアでは、ローマ帝国支配の名残でラテン語系言語が残った。周囲が山で囲まれていたため、スラブ化が進みにくかった。
- ハンガリーでは、ウラル系のマジャール人が定住。周囲の山脈に守られ、周囲とは異なる文化を育んだ。
ヨーロッパの河川

重要な国際河川
| ライン川 | 北ドイツ平原を流れ、スイス〜ドイツ〜オランダを貫く。国際河川として有名。 |
| エルベ川 | チェコのボヘミア盆地から北ドイツ平原へ。プラハやドレスデンを通る。 |
| ドナウ川 | ヨーロッパ中部〜東部を貫く大河。ウィーンやブダペストなどの都を結ぶ。 |

その他の特徴的な河川
| セーヌ川 | パリ盆地を流れる。フランスの中枢、パリの発展を支えた。 |
| ローヌ川 | アルプスから地中海へ。フランス南東部での農業や交易を支えた。 |
| テムズ川 | ロンドンを流れる。イギリスの経済と軍事の要所。 |
| ポー川 | イタリア北部を流れる。イタリア最大の農業地帯を支える河川。 |

ヨーロッパの気候
ここまで地形を見てきたが、それと同じくらい重要なのが「気候」。
なぜなら、気候は人々の暮らし方や農業の発展に直結するから。
参考:気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】
参考:気候をわかりやすく②:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【気候因子】
気候の大前提
温暖で雨が多い地域(農業がしやすい地域)は生活しやすく、人が集まりやすい。
ヨーロッパの気候の仕組み
北大西洋海流
偏西風
亜熱帯高圧帯
偏西風が吹く中緯度地域(緯度30〜60度くらいの地域)の大陸の西岸は、水(海)からの影響を受けやすくなる。
大陸の西岸には、陸地に比べて温まりにくく冷めにくいという性質を持つ海の上を通ってきた湿った空気(海洋性の空気)が流れ込む。その結果、大陸の西岸では気温の上昇・下降にブレーキがかかり、一年を通して穏やかな気候になりやすい。
地域ごとの気候区分

| 西ヨーロッパ | 西岸海洋性気候(Cfb):暖流(北大西洋海流)と偏西風の影響で、年間を通じて温暖・湿潤。 |
| 東ヨーロッパ | 冷帯湿潤気候(Df):大陸性の気候で、冬は寒く、夏はやや温暖。森林が多く、農業には不利な面もある。 |
| 北ヨーロッパ | 冷帯湿潤気候(Df):緯度が高いため、冬は寒く、日照時間が短い。森林が多く、農業には向かない。 |
| 南ヨーロッパ | 地中海性気候(Cs):夏は乾燥、冬は雨。オリーブやブドウなどの栽培に適している。 |
参考:アテネとリスボン、緯度はほとんど同じなのに…【地中海性気候】
まとめると・・・
ヨーロッパは全体として、起伏が小さく移動しやすい土地が多く、気候もそこまで厳しくない。つまり、人が暮らしやすい自然環境がそろっている。
(→だからこそ、この地域ではさまざまな人々が集まり、多くの「歴史」が生まれてきた)

参考:ヨーロッパの本質:なぜ争いから逃れられない地域なのか?
西ヨーロッパ

なかでも「フランス〜ドイツ西部」周辺は、ヨーロッパの中でも特に自然条件に恵まれている。広大な平野に複数の河川が流れ、温暖で農業に適した気候が広がる。
この環境が人の集中と都市の発展を促し、それが激しい対立や争いの舞台ともなってきた。
ちなみにオランダ周辺は、自然環境の厳しさと恵みが共存する場所。国土の多くは海抜が低く、昔から「水との戦い」が続いてきた。
一方で、地形は平坦で気候も温暖なため農業に適し、ライン川の河口という地理的優位性から物流面でも有利な立地となっている。



参考:なぜアムステルダムは自転車の街なのか?地理的に考察してみた
東ヨーロッパ

東ヨーロッパもまた、広大で平坦な地形が広がり、移動や耕作に適した環境ではある。しかし、気候は大陸性が強く、降水量が少なく乾燥し、冬は非常に寒くなるといった厳しさがある。
さらに、歴史的にもこの地域は西ヨーロッパのような交易の中心にはなれず、「農産物の供給基地」としての役割を担ってきた。
地理的にも、ドイツとロシアという2つの強大国の間に位置するため、戦争や侵略、支配の対象となりやすく、外からの影響に常に翻弄されてきた地域でもある。
こうした自然・経済・歴史の条件が重なり、産業基盤の形成が遅れ、経済発展の足かせとなってきた。その影響は現在でも色濃く残っている。

北ヨーロッパ

北ヨーロッパは、スカンディナヴィア山脈やフィヨルド地形など、険しく複雑な自然環境が広がる地域。寒冷な気候と短い夏、限られた耕地面積など、農業や大規模な都市・産業の発展には不利な条件がそろっている。
そのため、歴史的には経済発展の中心にはなれなかった。人口規模や経済規模の点で、「ヨーロッパの周縁」に位置する地域と言える。
南ヨーロッパ

地中海周辺の南ヨーロッパは変動帯に属し、火山が多く起伏が大きい。さらに、温暖な気候でありながら夏季の降水量が少ないため、水資源に乏しく、農業における制約が大きい。
このため、大規模な農業・工業・都市の展開が難しく、産業の集積も起こりにくい。加えて、山地が多いことで交通インフラの整備コストも高くなりやすく、沿岸部と内陸部の経済的な分断が生まれやすい。
こうした条件のもと、南ヨーロッパの国々(スペイン・イタリア・ギリシャなど)は、西や北のヨーロッパ諸国と比べて、全体として経済発展がやや遅れているのが現状である。
続き
ではこのようなエリアで、人々は具体的にどのような物語を繰り広げてきたか?(=争いまくったのか?)
→ヨーロッパの争いの歴史と、争いを防ぐための人類の知恵・試行錯誤











