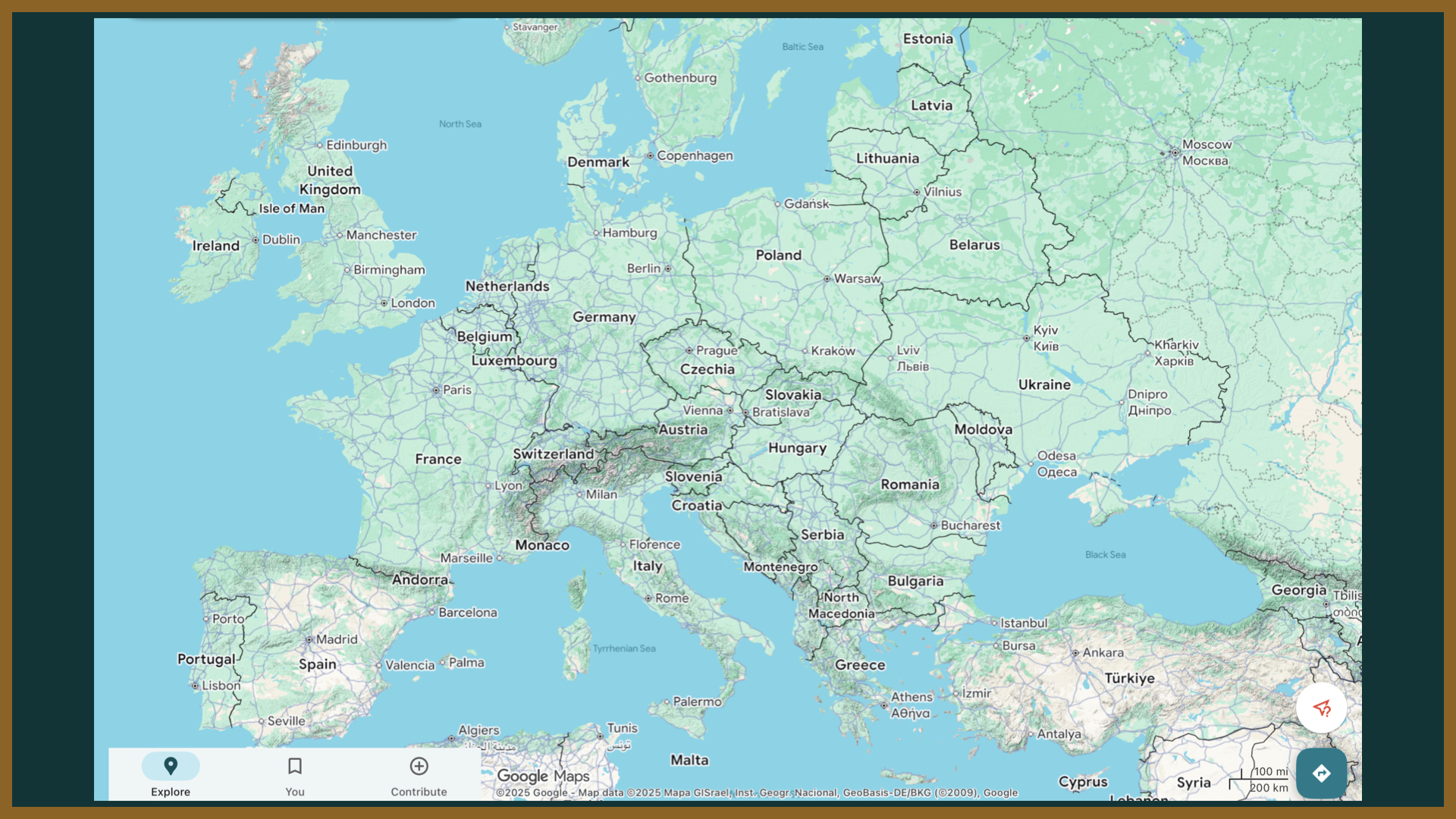なぜドイツ経済は強いのか?ヨーロッパ最強の工業国になっちゃう理由
ドイツは、第一次世界大戦、第二次世界大戦で大きな敗戦を経験し、国土も経済もボロボロになった国。
にもかかわらず、現在ではヨーロッパ最大の工業国であり、経済大国として君臨している。
なぜドイツは、こんなにも強いのか?
どうして最終的に、いつもヨーロッパで一番の経済力を持つ国になるのか?
今回は、「ドイツ経済はなぜ強いのか?」を地理・歴史・産業構造などの観点から、わかりやすく解説する。

地理的な優位性がある
工業に必要な資源が豊富
ドイツが工業大国となった大きな理由の一つに、地理的に「重工業に向いた場所」に位置していたことがある。
19世紀以降のヨーロッパでは、石炭と鉄鉱石が採れる地域を中心に重工業が発展した。
- ドイツのルール工業地域(←ルール炭田の石炭とライン川の水運)
- フランスのロレーヌ地方(←鉄鉱石)
- イギリスのミッドランド地方(←石炭と鉄鉱石)
- スウェーデンの南部(←キルナの鉄鉱石)

この中でも、ドイツ西部は条件が良かったと言える。
物流面で有利
ドイツ西部は、ルール炭田の石炭、ロレーヌの鉄鉱石という資源に加え、ライン川の水運を利用することができる。
- ライン川が優れている理由
-
- ライン川は船舶航行に適している(水量の安定、十分な川幅と深さ)
- ライン川は中部ヨーロッパを流れる国際河川で、流域には人口が密集し重要都市がいくつも形成されている
- ライン川の河口に位置するロッテルダム港はヨーロッパ最大の港(ロッテルダムはヨーロッパの玄関=「ユーロポート」)
- 1992年にはドナウ川と接続する運河(マイン=ドナウ運河)が完成した
また、ドイツはヨーロッパの中心に位置するため、交易の中心になりやすい。
このような地理的優位性をもっていたため、ドイツ西部では重工業が発達した(→「重工業三角地帯」と呼ばれる)。

※鉄を使って鉄道網をいち早く整備したことも、ドイツが工業国として他を圧倒する大きな理由だと思う。
※ロスチャイルド家(特にフランクフルト分家)は、ドイツやオーストリアをはじめとしたヨーロッパ各地の鉄道建設に深く関わっていた。鉄道投資を行う企業に資金を貸し付けたり、株式を引き受けたりしてインフラ建設を後押し。
工業の高度化がドイツをさらに強くした
その後、石炭から石油へのエネルギー革命や、1973年の石油危機により、「石炭や鉄鉱石がとれる地域での重工業」は衰退した。
代わって発展したのは、以下のような新しいタイプの工業。
| 港湾部を中心とした石油化学工業 | 例:オランダのロッテルダム、フランスのマルセイユ |
| 大消費地の近くで展開される先端技術産業・機械工業 | 例:ドイツのミュンヘン(自動車・電気機械)、ケルン(化学)、シュツットガルト(自動車) |
こうした「工業の高度化」によって、ドイツの工業的ポジションはさらに強化された。
なぜなら、先端技術産業や機械工業は、人件費の安さではなく、長年の技術蓄積と熟練労働力が競争力のカギだから。
- 長期的な技術投資が必要
- 教育・訓練によって支えられる高度な技能が必要
- 参入障壁が高く、他国が簡単にマネできない
その結果、ドイツは「簡単に参入できない領域=高付加価値産業」の分野で、圧倒的な競争力を持つことになった。
※ドイツは職業教育が盛んなことも、その傾向に拍車をかけた。

地域統合の取り組みがドイツをさらに強くした

ドイツが「ヨーロッパ工業の一強」となった背景には、地域統合(EU)の取り組みも大きく影響している。
EUは、「ヒト・モノ・カネの自由な移動」を実現することで、ヨーロッパ全体を一つの市場のようにしようとしている。この仕組みが、結果的にドイツの強さに拍車をかける働きをした。
【ヒト】自由な移動
ドイツ企業は、人件費の安い東ヨーロッパ(ポーランド・チェコなど)に工場を設けやすくなり、製造コストを抑えることが可能になった。
また、ドイツ国内にも他国から労働力が集まりやすくなり、人手不足の解消にもつながった。

【モノ】域内の関税撤廃
EU域内では関税が撤廃されているため、ドイツ製品を他国に安く・スムーズに売ることができる。

【カネ】共通通貨ユーロの導入

中学・高校の地理の教科書では語られていないが、超重要な視点!
EU域内の国々との貿易の際、為替の変動を気にせず、安定した取引ができる。
また、本来の自国通貨(マルク)よりも割安な通貨で輸出できる(※)。
※ユーロの価値(為替レート)は、ユーロを使っている国全体の平均的な経済力をもとに決まる。そのため、そのため、ドイツのように経済が強い国から見ると、「実力よりも安い通貨」で輸出できることになり、輸出が有利になる(※※)。
※※通常、経常黒字(輸出超過)が大きければ、外国からの需要によりその国の通貨は買われ、通貨高(為替の上昇)になる。
- なぜ経常黒字(輸出超過)になると通貨が買われるのか?
-
輸出すると、外貨で代金が支払われる
- ドイツが例えば日本に車を輸出すると、ドイツ企業は「ユーロ」で代金を受け取りたい。でも、日本は「円」が流通している国。
- →日本の会社は、円を売ってユーロを買う必要がある。
つまり、輸出が増えると「ユーロを買う人」が増える
- ドイツが多くの国にモノを輸出しているということは、各国で「自国通貨を売ってユーロを買う」取引が多く発生しているということ。
- つまり、ユーロに対する需要が高まっていることを意味する。
通貨も「需要が増えると価格が上がる」
- たくさん欲しい人がいれば、モノの値段は上がる。
- 通貨でも同じで、「買いたい人」が増えると通貨高になる。
輸出が多い=その国の通貨を「買いたい人」が多い
結果としてその通貨が高くなる(=通貨高)
参考:ヨーロッパ統合の目的をわかりやすく:なぜベネルクスから始まった?

結果として、EUのおかげで、ドイツは「高品質な製品を、為替的にお買い得な価格で世界中に売る」ことが可能になっていると言える。
これが、ユーロ導入が「ドイツ製品の国際競争力を不当に高めている」と批判される理由となっている。
参考:かつては“欧州の病人”、今や“一人勝ち” その国は?(NHK)
参考:ヨーロッパの工業をわかりやすく:ドイツが強すぎることの何が問題?
参考:ヨーロッパ連合(EU)の問題点をわかりやすく:なぜ格差が拡大する?