なぜ中国共産党は人の「数」や「移動」をコントロールしようとする?
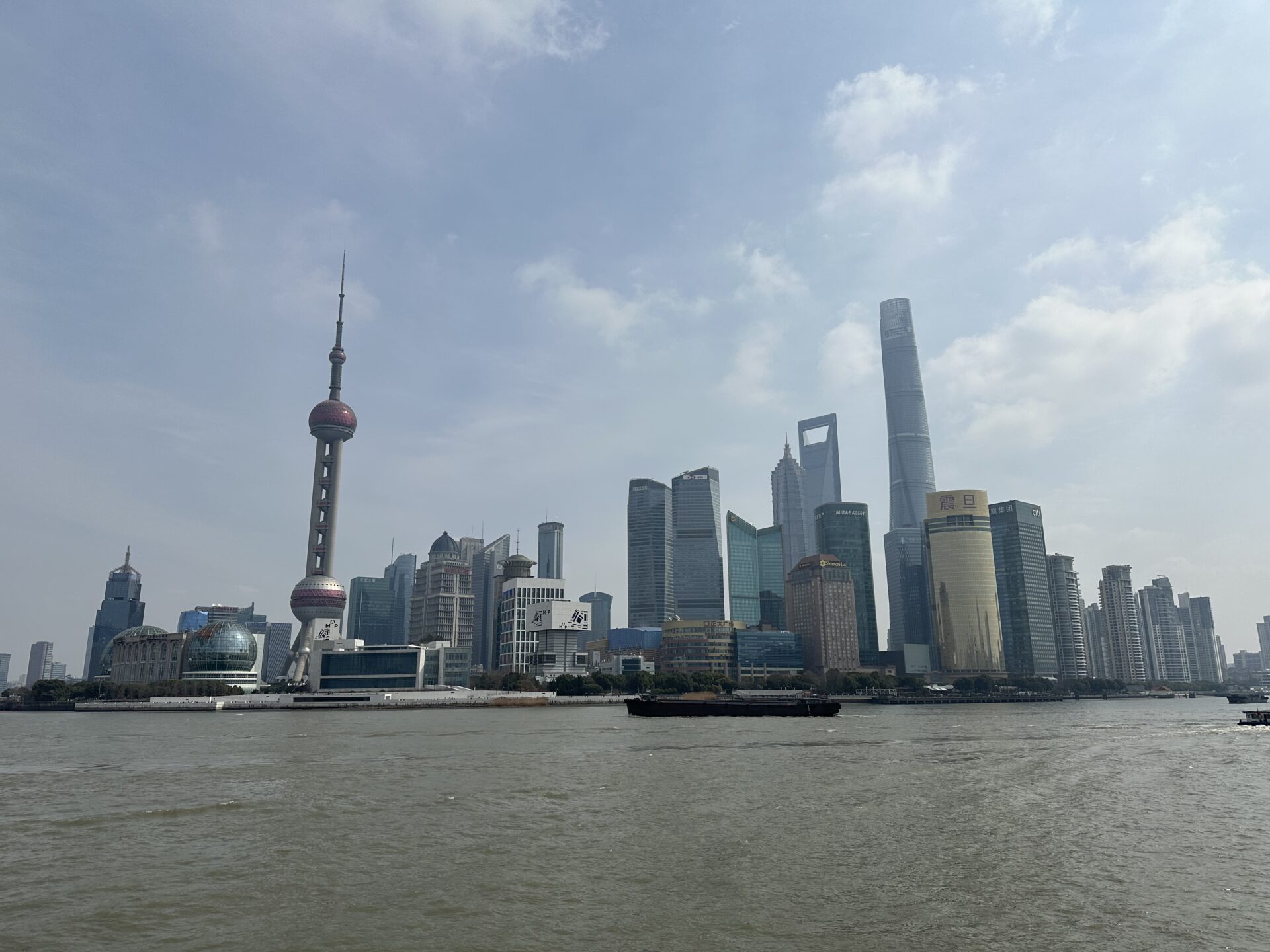
中国といえば、世界有数の人口を持つ巨大国家。
でも、そんな「人の多さ」が、実は中国共産党にとっての脅威となっている。
中国共産党は「人」の脅威を感じている
中国では、基本的に人口はどんどん増えていった。
でも、中国共産党にとってそれは単なる「成長」ではなく、コントロール困難な脅威でもある。
人口が増えすぎるという脅威
例外的に人口が増えなかった(減少した)時期は2つだけ。
- 1949年以前:医療や衛生が整わず「多産多死」だったため、大きくは増えなかった
- 1959~62年:「大躍進政策」の失敗、飢饉により、大量の死者が出た
この2つの時期を除けば、人口は爆発的に増加していった。
人が増えすぎると国家が管理できない。だから怖い。
人口分布が偏るという脅威
中国では、人口が国土全体にバランスよく分布しているわけではない。圧倒的に東部に偏っている。
なぜなら、東部は
- 平野が広がり、住みやすく、農業も発展
- 海に近く、港湾や貿易がしやすい
- 気候が比較的安定している
といった理由で、自然環境に恵まれているから。
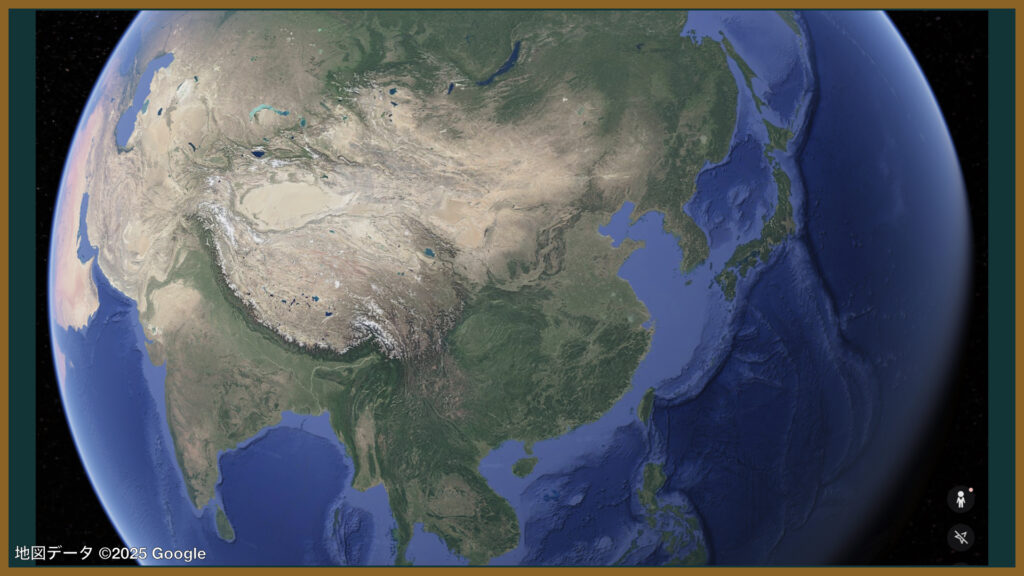
人口の分布が偏りすぎると(=都市に人が集まりすぎると)、以下のような問題が起こる。
- 教育や医療が足りない
- 住宅が不足してスラム化
- インフラがパンク
- 治安悪化や暴動のリスク
- 年金・医療などの社会保障費が急増
逆に、農村部は過疎化して、農業生産や地方経済が弱体化していってしまう。
中国の重要都市
以下は、特に人口が集中しやすい重要都市や地域である。
4つの直轄市
| 北京(ペキン) | 首都。政治・経済・文化・交通の中心地。 |
| 天津(テンチン) | 港湾・商工業都市。北京の外港で、河北最大の貿易港。 |
| 上海(シャンハイ) | 長江の三角州に位置する。最大の港湾・商工業都市。19世紀にアヘン戦争敗北で開港され、欧米諸国が進出。浦東(プートン)地区は輸出加工区・外国企業投資区などが建設されている。 |
| 重慶(チョンチン) | 四川(スーチョワン)盆地南東部に位置する。商工業都市。長江中流の水陸交通の要地。 |

5つの経済特区
| 深圳(シェンチェン) | 1979年に指定。香港に隣接。 |
| 珠海(チューハイ) | 1979年に指定。マカオに隣接。 |
| 汕頭(スワトウ) | 1979年に指定。 |
| 廈門(アモイ) | 1979年に指定。台湾の対岸に位置。 |
| 海南省(ハイナン) | 1988年に指定。「中国のハワイ」と言われるくらい観光業が盛んなリゾート地。 |

2つの特別行政区
| 香港 | 旧イギリス植民地。1997年に中国に返還。中継ぎ貿易港として発展。2020年に「国家安全維持法」が導入され、「一国二制度」が事実上終了した。 |
| マカオ | 旧ポルトガル植民地。1999年に中国に返還。 |
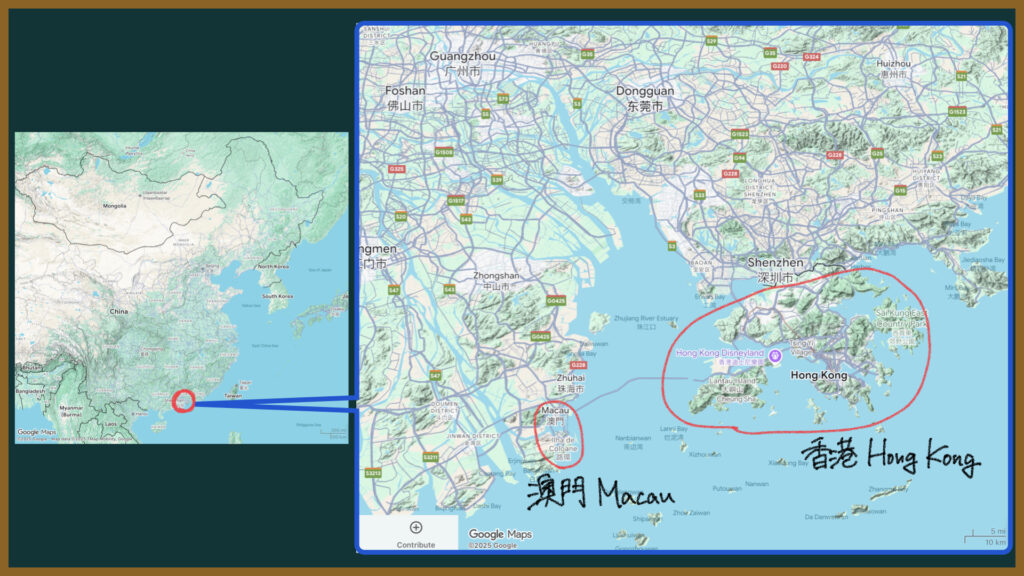
中国共産党の人口管理政策
人口が増えすぎたり、都市に集中しすぎたりするのを防ぐために、中国はさまざまな政策を行ってきた。
人の移動を管理・制限
戸籍制度
中国人に自由な移動を認めると、いろんな意味で恵まれている都市に人が集まりすぎてしまい、農村が過疎化してしまう。
それを防ぐため、1958年に「戸籍(戸口)制度」が導入された。これにより、すべての国民は出生時に「都市戸籍」か「農村戸籍」に登録されることになった。
- 都市への人口流入を制限
- 都市戸籍者には手厚い社会保障(年金・医療など)を与える
- 農村人口を維持し、農業・地方経済を守る
つまり、戸籍制度は「農村の人々を都市に移動させない仕組み」である。
中国共産党が戸籍制度を今でも完全には廃止しないのは、社会のバランスが崩壊することを恐れているから。
- 農民工(都市部で働く農村出身者)
-
戸籍は農村戸籍のまま、都市に出稼ぎに行く人々。主に建設業・工場・清掃・配送などの 労働集約型産業に従事。
農村の集団化
中国では1950年代後半から、毛沢東のもとで農村を人民公社として集団化した。
これは農業の効率化・国家の食糧確保のために導入されたが、同時に「農村人口を農村にとどめる」ための仕組みとしても機能した。
- 人民公社は、労働・生活・教育・福祉などをすべて村単位で完結させることを目指した組織。
- 住民はその中で働き、住み、暮らすので、自由に都市へ出ていくことができない。
人口の増加を管理・制限
一人っ子政策(1979〜2014)
人口増加を抑制するために、少数民族を除いて出産を一人に制限した。
- 一組の夫婦に子供は一人まで
- 二人目を産むと罰金などのペナルティ
- 一人っ子家庭には教育や住宅などで優遇措置
ところが・・・
人口の年齢構成の変化(少子高齢化)
人口増加を抑えるために出生数を制限した結果、若者が減り、医療や年金を必要とする高齢者が急増する、という少子高齢化が急速に進行した。
中国は「人口の年齢構成の偏り」という別の人口問題に直面することになったのである。
そこで、このままでは経済も社会も持たない!ということで一人っ子政策は廃止された。
- 2015年:一組の夫婦につき子供は二人までとされた
- 2021年:3人目の子供を出産することを認めた
しかし、
- 若者が結婚したがらない
- 物価が高くて子育てが負担
- 都市部での教育競争が激化
といった理由で、子供を産まない家庭が増えている。
まとめ:中国にとって「人」は最大の資源であり、最大の脅威
中国が抱える大量の人口は、経済を支える「力」であると同時に、暴動・貧困というリスク要因でもある。
中国は、「どうすれば、この広すぎる土地と、多すぎる人々を1つにまとめられるか?」というテーマでずっと悩んでいる。











