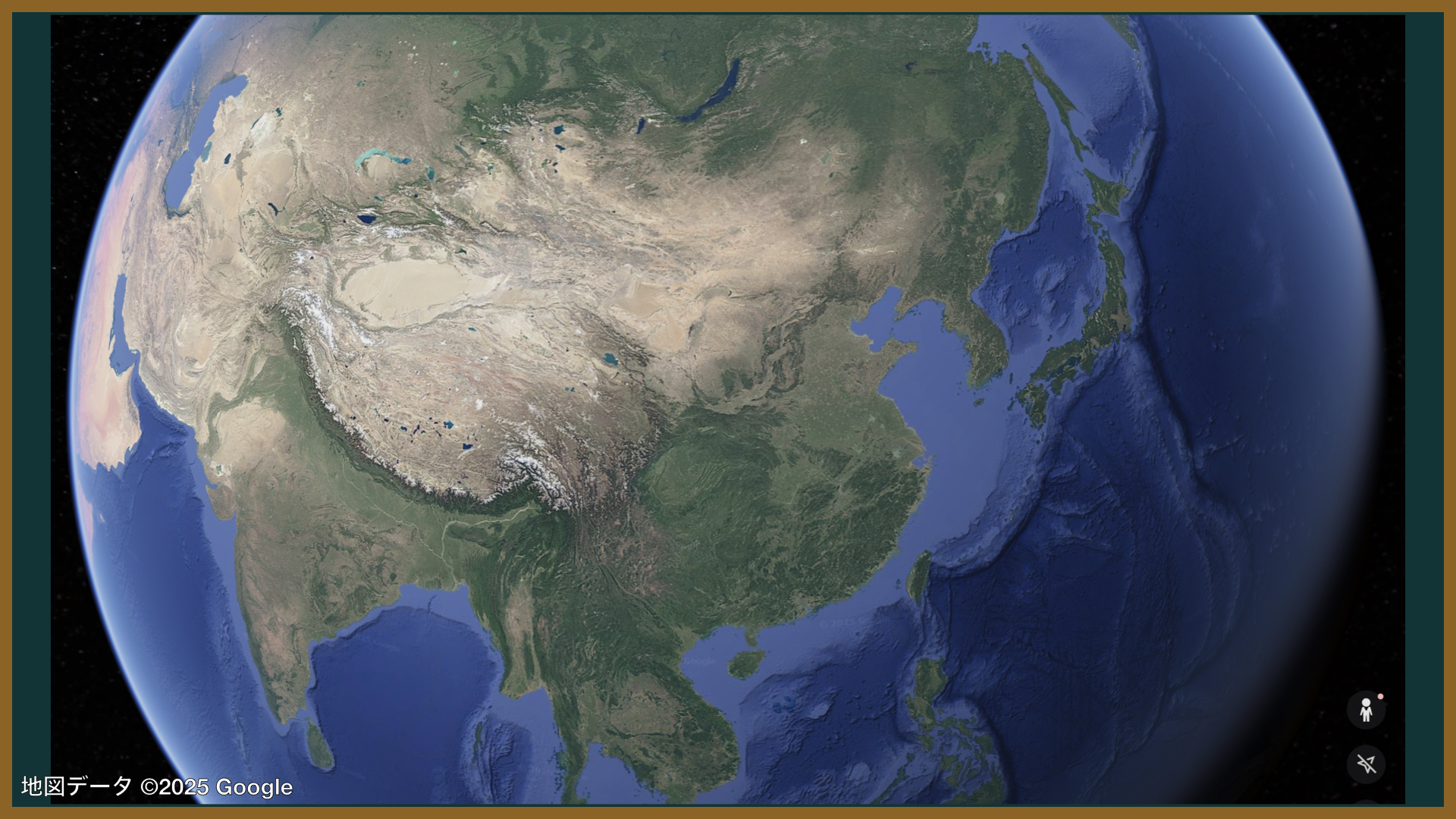西アジア(中東)の鉱工業をわかりやすく:なぜ石油大国・石油依存になった?
西アジアと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「石油」だろう。
しかし、なぜ西アジアはこれほどまでに石油に頼る経済になったのだろうか?
石油が見つかる前の西アジアには、強い産業がなかった
石油が脚光を浴びる以前、西アジアは工業化の波に乗り遅れていた。その理由はいくつかある。

資源の不足
まず、工業化に必要な資源が不足していた。
西アジアの大部分は乾燥地帯であり、工業の動力源となる石炭や水、そして鉄鋼業に不可欠な鉄鉱石といった資源が乏しかった。そのため、大規模な工業は育たなかった。
陶器やタイルなどの工芸品づくりは盛んだったが、外部からの資源(木材・金属)に頼る小規模な産業にとどまった。

改革力の不足
次に、歴史的な要因である。
大航海時代以降、ヨーロッパが東アジアと直接交易するようになると、西アジアの「東西交易の拠点」としての重要性は低下した。
さらに、19世紀にはヨーロッパ列強の影響下に置かれ、自立した経済発展が難しい状況だった。
このように、西アジアは農業や交易が中心の経済のまま、20世紀を迎えることになる。
石油大国になった理由
そんな西アジアの運命を一変させたのが、20世紀初頭に本格化した石油開発である。
この地域が世界最大の産油地帯となったのには、明確な理由がある。

地質が特殊
ペルシア湾沿岸は、数億年前の中生代に、浅い海だった。
この海に生息していた大量のプランクトンや生物の遺骸が海底に沈み、それが長い時間をかけて変化し、石油のもととなる「有機物」を大量に含んだ地層となった。

さらに、ペルシア湾周辺はユーラシア大陸とアラビア半島がぶつかり合う地帯である。
プレート同士の衝突により、地層が押し曲げられ、まるで皿のような形になった。これを背斜構造と呼ぶ。この構造が、地下で生成された石油を効率的に閉じ込める「天然の貯蔵庫」として機能した。
このように、二つの条件が偶然にも重なったことで、西アジアは「世界一の油田地帯」になった。
外国の技術と資本が導入された
莫大な量の石油が眠っていても、それを掘り出すには膨大な資金と高度な技術が必要である。しかし、20世紀初頭の西アジア諸国にはそのどちらもなかった。
また、西アジアの王や首長たちは、石油の本当の価値を理解できていなかった。
そのため、アメリカやイギリスの巨大企業、いわゆる「国際石油資本(メジャー)」が、技術と資本を投じて石油開発を独占的に進めた。彼らは、現地の王や首長と不利な契約を結び、莫大な利益を得ることに成功した。
※その後、産油国が力を合わせてOPEC(石油輸出国機構)を結成し、自らの主導権を取り戻すまでには、長い時間がかかった。
「資源の呪い」
石油収入は国家を潤し、人々の生活を劇的に向上させた。
しかし、それは同時に、「石油さえあれば他に産業は必要ない」という発想を生み出し、経済を石油に一本足打法へと向かわせるきっかけとなった。
さらに、石油収入を国民に分配することで、国民の不満を抑えつつ権力を維持する「石油依存型」の強権的政治体制も生まれた。
これは「資源の呪い」と呼ばれる現象の典型的な例である。豊富な資源が、かえって健全な経済や民主主義の発展を妨げてしまうことを意味する。
このように、西アジアが石油大国となった背景には、偶然の地質的条件、そしてそれを開発した外国資本、さらにはその後の政治・経済の選択が複雑に絡み合っている。
まとめ
工業の基盤が弱かった
→石油が地質的に多かった
→外国資本が掘って開発を進めた
→その後国有化しつつも独裁体制で石油依存が固定化