日本はエネルギーを何から手に入れ、何に使っている?【エネルギー供給・消費】
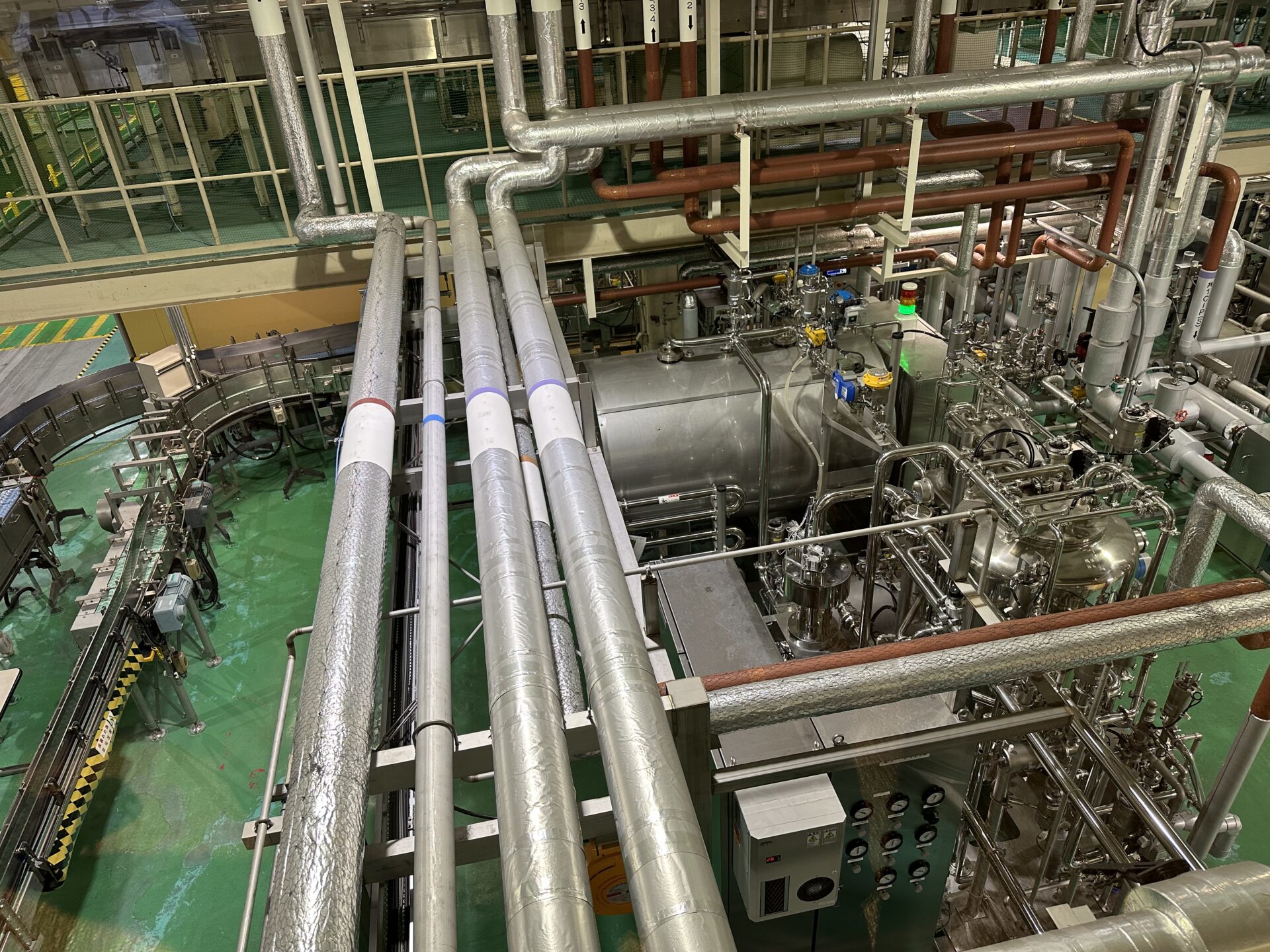
エネルギー白書を見るのが一番いい!
→エネルギー白書にわかりやすくまとまっている。
ざっくり言うと
エネルギーの約8割を化石燃料から得ていて、約6割を産業(運輸を除く)に使っている。
エネルギーを何から手に入れている?(エネルギー供給)※2022
化石燃料:約83%
- 石油:約35%
- 石炭:約25%
- 天然ガス:約20%
非化石:約17%
- 再生可能エネルギー:約10%
- 水力:約3%
- 原子力:約3%
エネルギーを何に使っている?(エネルギー消費)※2022
運輸部門:約23%
=自動車、鉄道、航空機などの交通機関でのエネルギー使用

- 電気自動車が普及して運輸部門での化石燃料の使用が減ったとしても、電力への変換ロスがある以上、トータルではエネルギー消費は増えるのではないでしょうか?
-
電気自動車(EV)に切り替えたほうが、トータルのエネルギー消費は減る可能性が高い。
- ガソリンエンジンは、燃料に含まれるエネルギーのうち約2~3割しか車輪を回すのに使えていない。
- 残りの7~8割は、熱や摩擦などでムダになっている。
一方、
- 電動モーターは、入力された電気エネルギーの8~9割を車輪を回すのに使える。
- 発電から充電までのロス(発電ロス・送電ロス・充電ロス)を含めても、全体の効率はガソリン車よりずっと高い。
- 電気自動車は高出力を出しにくいという弱点があると言われますが、高出力がないと困る場面って一般にあるのでしょうか?
-
まず前提として、
- モーター自体は出力の立ち上がりが非常に速い(つまり、瞬発力はエンジンよりも優れている)。
- 「出しにくい」と言われるのは、長時間・大出力を出し続けるとバッテリーが厳しいという意味バッテリー負荷が高くなり、熱や劣化リスクが問題になる。
では、一般人が乗る車で「高出力が必要な場面」はあるのか?というと、日常生活ではほとんどない。
高出力が必要なのは、以下のような限られた状況のみ。
シーン なぜ高出力がいるか? レースやスポーツ走行 一気にスピードを上げたり、トップスピードを維持したりするため トレーラー・大型トラックの牽引 重い荷物を引っぱるため 山道で超急坂を長時間登る エンジンやモーターに大きな負荷がかかる 砂漠やオフロード走行 悪路で大出力が必要になる
- すべての自動車が電気自動車に置き換わるのではなく、用途ごとに使い分けるのが妥当ということでしょうか?
-
すべての自動車を無理にEVにするのではなく、用途ごとにエネルギー源を最適化して使い分ける
→ これが最も現実的で合理的な戦略。
車の種類 エネルギー源(今後の主流イメージ) 理由 乗用車(一般家庭用) 電気自動車(EV) 日常使いの距離・パワーならEVで十分。環境負荷も小さい。 小型配送車(ラストワンマイル配送など) EV or 水素(FCV) 距離が短く、こまめな充電・補給ができるから。 長距離大型トラック・バス ディーゼル or 水素燃料電池(FCV) 長時間・大出力が必要なので、現状はEVだとバッテリーが重すぎる。 特殊用途車(工事車両・山岳地帯の車など) ディーゼル or ハイブリッド 安定した大出力・燃料補給のしやすさが必要。 高速道路の超長距離輸送 水素燃料電池(FCV)が有力 水素は短時間で補給でき、長距離にも耐えやすい。
- 自動車を作るのにも大量のエネルギーが使われていると思うので、むやみに自動車を持つのではなく、シェアリングなどを通して自動車保有台数をトータルで減らすというのも、有効なエネルギー節約方法ですよね?
-
1台の自動車を作るには、ものすごい量のエネルギーが使われる。
- 鉄、アルミ、プラスチックなどの素材を作るエネルギー(原料の採掘・精錬)
- 工場で組み立てるエネルギー(電気・熱)
- 工場や輸送のための間接エネルギー
つまり、「走る時のエネルギー」だけじゃなく、「作る時のエネルギー」も膨大。
だから、「自動車保有台数を減らす」ことがエネルギー節約になる。
家庭部門:約15%
=住宅での電気やガスの使用。

- エネルギー消費を減らしたい時に、家庭で省エネのようなことをしても、インパクトとしては小さいということですよね?
-
家庭部門での消費は約15%しかないので、家庭でどれだけ省エネしても、社会全体に与えるインパクトはそこまで大きくない。
本当にエネルギー消費量を減らしたいなら、産業・運輸の大規模な省エネ改革が不可欠。
業務他部門:約16%
=第三次産業でのエネルギー使用

- 日本でデータセンターの建設が相次いでいますが、データセンターの電力消費は業務他部門に分類されますか?
-
データセンターは「サービス業(情報サービス業)」に該当する施設。発電所や工場のような「ものを作る産業」ではないので、オフィスビルや商業施設などと同じ扱いとなり、業務他部門にカウントされる。
- データセンターは巨大なサーバー群を24時間稼働させるため、ものすごく電力を消費する。
- 特に冷却(空調)にも大量の電力が必要。
→データセンターの急増=業務他部門の電力消費の増加要因になっている。
※データセンター=インターネット上の情報やサービスを管理・処理するための、大規模なコンピューター施設。サーバー(ネット上のコンピューター)をたくさん設置してウェブサイト、SNS、動画サービス、クラウドストレージなどを動かしたり、銀行や病院、企業の情報システムを安全に保管・運用したりしている。
なぜわざわざ専用の施設を作るのか?
大量のコンピューターを安定して動かすには、電力供給が安定し、ネット回線が超高速であることが必要。また、コンピューターは熱を出すので、冷却設備(空調)が強力でなければならない。さらに、停電や地震、火災などにも備えた超高レベルのセキュリティと耐障害性が求められる。
- 日本国内でのデータセンターの建設はどのような場所で行われていますか?
-
関東地方:データセンターの主要な集積地
- 東京都心部:大手町や品川など
- 千葉県印西市:地盤が強固で災害リスクが低く、都心からのアクセスも良好
- 埼玉県さいたま市や神奈川県川崎市・横浜市:データセンターの開発や用地取得が活発化
関西地方
- 大阪市:堂島など
- 京都府相楽郡:NTTが新たなデータセンターを建設中
北海道:冷涼な気候を活かし、空調コストの削減が可能なため、データセンターの立地先として注目されている
- 石狩市:さくらインターネットが大規模なデータセンターを運営
- 苫小牧市:ソフトバンクとIDCフロンティアが日本最大級のデータセンターを建設中
産業部門:約45%
=製造業、農林水産業、鉱業、建設業でのエネルギー使用
特に製造業が多い。

- 製造業が海外移転したら、見かけ上はその国の産業部門のエネルギー消費は減少しますよね?
-
製造業の海外移転は、国内のエネルギー消費を減らすが、世界のエネルギー消費問題を解決するものではない。
- 製造業(工場)が海外に移転すると、その国(たとえば日本)の国内産業部門のエネルギー消費は減少する。
- ただし、工場が移っただけで、世界全体ではエネルギー消費は減っていない。
- むしろ、新しい生産地ではエネルギー効率が悪かったり、CO₂排出が多かったりすることもある(例:中国の石炭火力ベースの工場など)。
- 中国のエネルギー消費が急増したのは、産業部門でのエネルギー消費が増えたからですよね?
-
工場がたくさん建ち、モノを大量に作るためにものすごい量のエネルギー(主に石炭・電力・石油)が必要になった。これが、中国のエネルギー消費増大の一番大きな要因。
- 1990年代後半から2000年代にかけて、中国は「世界の工場」と呼ばれるようになった。
- 鉄鋼、セメント、化学製品、自動車、電子機器など、あらゆる分野で膨大な製造業が拡大。
- 特に重工業は電力や燃料を非常に大量に消費する。
- 中国は発電に石炭火力を大量に使っているため、石炭消費が爆発的に増えた。
- 経済発展によって中国の人々の生活水準が向上し、家庭部門でのエネルギー消費が増えたこともあるが、それよりも産業部門での増大の方がインパクトとしては大きいということですよね?
-
YES!
- サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国が砂漠に大都市を作ろうとしていますが、あれはエネルギーを膨大に使うのであまり良いことではないですよね?特に海水の淡水化のエネルギー消費は激しそうです。
-
砂漠都市は「エネルギーの大量投入ありき」で成立している。環境負荷が大きく、持続可能性の観点からは非常に大きな課題がある。しかし、国家の生き残り戦略として自然環境的に無理があるのは承知の上で挑戦している。
1.淡水化
- 砂漠では水がないので、海水を淡水化(真水にする)して使う。
- これには莫大なエネルギー(主に電力・熱)が必要。
- 特に中東で主流の「逆浸透膜(RO方式)」や「多段式蒸留法(MSF方式)」は、 1立方メートル(1000リットル)の水を作るのに2〜4kWhくらいの電力が必要。
→つまり、街の人口が増えれば増えるほど、飲み水を作るためだけに大量のエネルギーが必要になる。
2.冷房
- 砂漠は猛烈に暑い(夏は50℃超えも珍しくない)。
- だから、冷房(エアコン)の需要が桁違いに高い。
- 家庭・ビル・ショッピングモール・公共交通機関…至るところで冷房が必須。
→これもまた、膨大な電力消費に直結する。
3.食料や建材の輸送
- 砂漠ではほとんど農業ができないので、食料を大量に輸入しなければならない。
- 建材も地元調達が難しいので、輸入に頼る→これも間接的にエネルギー消費(輸送エネルギー)が大きい。












